|
|

2005.11 |
立岩橋
鬼怒川
国道121号のバイパス
ホテルのベランダから。
鬼怒川ライン下りから見上げた立岩橋 |

2005.11 |
神橋
大谷川
日光二荒山神社
東照宮などからの帰り道,観光バスの車窓から。 |
|
|

2006.11 |
平戸大橋
平戸瀬戸
国道383号 (橋部分は平戸大橋有料道路 : 普通車 100円)
平戸側たもとに整備された平戸大橋公園から。
夕方の遠景。手前は平戸瀬戸に浮かぶ黒子島。
黒子島から昇る朝日。 |
|
|

2007.04 |
大鳴門橋
鳴門海峡
神戸淡路鳴門自動車道
鳴門公園,千畳敷から。
対岸,淡路島から遠望する。 |

2007.04 |
かずら橋
祖谷川
平家の落人がシラクチカズラを編んで架けたともいわれる吊橋。
足元はこんな具合。
これは確かにコワい。渡る観光客はみな顔がこわばっている。
あいにくの雨。
渡橋料 : 500円(大人) |

2007.04 |
高瀬沈下橋
四万十川
増水時に川に沈んでしまうように設計された欄干のない橋が,いわゆる沈下橋。
四万十川には47ヶ所もあって,高瀬の沈下橋は3番目に長い。
四万十川遊覧船の屋形船に乗る。「なっとく」乗船場と沈下橋遠景。
この橋を車で走り渡るのは,想像しただけでお尻がムズ痒くなる。。。
増水を始めて水位が沈下橋の橋板スレスレになった時が大変危険で、川に目を配るとスーッと川に吸いこまれそうになります。増水時には渡らないようにしましょう。
(高知県文化環境部「四万十川の姿-沈下橋」より) |
_a1.jpg)
2007.10 |
新橋
松江堀川
城があり堀がある古い街並みであればなんの変哲もない橋なのかもしれないが。
「ぐるっと松江・堀川めぐり」。女船頭さんの案内で,23ヶの橋を楽しんだ。
ふれあい広場乗船場を発着すると,最初と最後にくぐるのが新橋。
なかには身を伏せなければいけないほどの低い橋もある。 |

2007.10 |
錦帯橋
錦川
岩国城下,木造の5連アーチ橋。
観光バスの駐車場になっている河川敷から。
向こうの山の上にあるのが岩国城。
接近すると,木造橋であることがよく分かる。
入橋料 : 300円(大人) |
|
|

2008.10 |
的矢湾大橋
的矢湾
パールロード
明け方,ホテル最上階から。
対岸の山の上には志摩スペイン村が(行かなかった…)。 |

2008.10 |
振ヶ瀬橋
熊野古道大門坂
熊野那智大社への登り道の入口。
私たちは小雨の中を下ってきたが,コケむした石段が滑りやすくてかえってくたびれた。 |

2008.10 |
御廟橋
高野山奥の院参道
お大師様がこの橋まで迎えに来てくれるという。
伊勢神宮にしても奥の院にしても,「ここから先は撮影禁止」という意味がよく分からない。
室内ならともかく… |
|
|
|
|
_a1.jpg) |
新橋
吉田川
町を出てすぐ長良川に注ぐ吉田川は子どもたちの水遊びの場。
新橋下のこの深みめがけて,度胸試しの子どもたちが飛び込む。 |
 |
清水橋
小駄良川(吉田川支流)
室町時代の故事を伝える宗祇水。
今でもこんこんと湧き出す泉のそばに,この橋がある。 |
飛騨高山の古い町並を散策しながら出会った橋たち |
2009.10 |
|
_a1.jpg) |
中橋
宮川
上三之町からこの橋を渡ると高山陣屋跡。山岡鉄舟の銅像が立つ。
地域のおじさん,おばさんの小遣い稼ぎの場,朝市で賑わう。 |
 |
鍛冶橋
宮川
欄干の上流側テナヅチが坐り,下流側にはアシナヅチが立つ。 |
|
|
 |
河童橋
梓川
穂高連峰を望み,上高地を象徴する吊り橋。
いろいろな角度から・・・①,②,③
上高地はかつて神河内と書かれたそうな。 |
|
|
 |
新山彦橋
黒部川
宇奈月駅を出たトロッコ電車が最初に渡る鉄橋。
1986年(昭和61年)完成の上路トラスドアーチ橋。
この写真は,宇奈月駅へ向かう帰りの電車から。
重なって向こうに見えるのは旧・山彦橋。 |
 |
山彦橋
黒部川
新山彦橋を渡る電車から眺める。
かつてはこちらが鉄道橋だったが,今では散策路として使われているらしい。
さらにその奥にも,支流にかかる橋が見える。 |
 |
宇奈月ダム湖面橋
黒部川
真っ赤なバスケットハンドル型ニールセンローゼ橋。
宇奈月ダム湖を横断する。
トロッコ電車から眺めるだけでは物足りない… |
 |
猿専用の吊橋
黒部川
写真の手前の橋が猿専用。
宇奈月ダム湖の上,高さ15m。手すりは,ない。。。
2005年(平成17年)完成。しっかり利用されているらしい。 |
 |
跡曳水路橋
黒薙川(黒部川支流)
鉄筋コンクリート・アーチ橋。
トロッコ電車が渡る後曳橋と並行して架かっている。
1927年(昭和2年)建造という。いかにも古色蒼然たる橋である。
黒部川第二発電所下から新柳河原発電所へと曳かれる発電用水路と思われる。 |
 |
目黒橋
黒部川
数少ないフィーレンディール橋のひとつ。
黒部川第二発電所に通ずる鉄橋で,1934年(昭和9年)竣工。
1936年(昭和11年)竣工の黒部川第二発電所の建物は,富山の建築百選に選定されるなど名高い。
深い峡谷の中に,真っ赤な橋梁と真っ白な建物の緊張感漂う対比。
いつまで見ていても見飽きることがなさそう。
しかし時速20kmほどとはいえトロッコ電車はゴトゴト進み,いつまでもは眺められない。 |
|
|
日田市豆田町に通じる花月川に架かる橋 |
2010.12 |
|
 |
一新橋
花月川
江戸時代は大橋と呼ばれて親しまれていた。
九州といえば焼酎一色と思いきや,元禄のころから清酒を造り続けてきたという酒蔵が一新橋のたもとにあった。 |
 |
御幸橋
花月川
江戸時代は殿橋と呼ばれていた。
一新橋につながる路を豆田上町通り,御幸橋につながる道を豆田みゆき通りと呼ぶらしい。 |
|
|
 |
橋名不詳
大分川
大分川の源流に架かる木造の人道橋。
名前も定かではないちっぽけな橋だけれど,金鱗湖周辺の散策には欠かせない。
金鱗湖はこの朝も朝霧に包まれていた。 |
|
|
 |
高千穂三代橋
五ヶ瀬川
造られた年代も,材質も,大きさもすべて異なる3つのアーチ橋
神橋架設は大正年代との記述が多い。その後架け直されたものだろう。
| 神都高千穂大橋 |
(写真中) |
コンクリート橋 |
平成15 |
長さ300m |
高さ115m |
| 高千穂大橋 |
(写真上) |
鋼橋 |
昭和30 |
96m |
75m |
| 神橋 |
(写真下) |
石橋 |
昭和22 |
31m |
31m |
|
 |
槍飛橋
五ヶ瀬川
五ヶ瀬川の中でもっとも川幅が狭いところだという。 |
 |
御橋
五ヶ瀬川
橋から見下ろすとボートが浮かぶ。
真名井の滝はここからも眺望できる。 |
|
|
 |
弥生橋
鬼の洗濯岩
昭和53年竣工。これにより,満潮時でも青島が陸続きになった。
早朝の青島。陽が昇り始める。
生憎の満潮で,洗濯板は見え隠れ。 |
|
|
 |
塩浸温泉橋
石坂川
この年(3月)完成したばかり。
みえみえの龍馬人気あやかりスポット。
龍馬資料館『この世の外』とか,縁結びの足湯とかがある。 |
長崎平和公園の南端を流れる小川に架かる橋 |
2010.12 |
|
 |
緑橋
下の川(しものかわ)
昭和61年架設。
下の川はほとんど爆心地直下を流れている。
原爆の惨状は筆舌に尽くしがたいものがあったに違いない。
緑橋架設とともに施工された護岸には,被爆当時の石が用いられているという。
誓いの火をはじめ,多くのモニュメントや石碑が並ぶ坂を上ると長崎原爆資料館が建つ。 |
長崎中島川に架かる石橋群
かつては14橋あったというが,現在は11橋。
第10橋の眼鏡橋から第5橋の古町橋までの6橋を渡ってみることができた。
どの橋も,洪水などで損壊し何度か修復を繰り返されている。 |
2010.12 |
|
 |
袋橋
中島川
眼鏡橋に次いで古いともいわれる。
現橋は1985年(昭和60年)に復元されたもの。車も走る。
眼鏡橋から望む。 |
 |
眼鏡橋
中島川
日本最古の石造アーチ橋。
1634年(寛永11年),唐僧黙子如定により架設されたとされる。像が立つ。
現橋は1983年(昭和58年)に復元されたもの。
上流側の流れの中に撮影ポイントとしての置石が用意されている。
下流から眺める。 |
 |
魚市橋
中島川
元禄年代(1699)に架設。
現橋は1939年(大正14年)に架け直されたもの。
この橋だけは見た目にも石造アーチではなく,車も走る鉄筋コンクリート橋である。
下流から見上げる。 |
 |
東新橋
中島川
寛文年代(1673)架設。
現橋は1968年(昭和61年)に昭和の石橋として復元されたもの。 |
 |
芊原 (すすきはら) 橋
中島川
延宝年代(1681)架設。
現橋は1968年(昭和61年)に復元されたもの。
石造アーチに擬した鉄筋コンクリート橋。車も走る。 |
 |
一覧橋
中島川
明暦年代(1657)架設。
現橋は1968年(昭和61年)に昭和の石橋として復元されたもの。
中国原産の石材(花崗岩)を使用しているという。 |
 |
古町橋
中島川
元禄年代(1697)架設。旧親柱。
現橋は1968年(昭和61年)に昭和の石橋として復元されたもの。
橋の側面に蔦などの植物が這い茂り風情がある。 |
 |
編笠橋
中島川
元禄年代(1699)架設。
現橋は1968年(昭和61年)に昭和の石橋として復元されたもの。
古町橋から望む。 |
|
|
|
|
 |
中島遊歩道橋
十三湖
中央部にアーチが配された味わいのある木造橋。車両も通行するらしい。
十三湖は津軽半島で最大の汽水湖。しじみの産地だけに"しじみ汁"が有名。
北西部に浮かぶ中ノ島には土師器(はじき)などが出土する奈良時代の遺跡がある。 |
今回のみちのくツアーではあまりにも橋が不作だった。寂しすぎる。。。
階段になっているので車はとても走れないという不可思議な国道339号に特別出演していただこう。 |
|
|
 |
階段国道
龍飛崎
全長388.2m,段数362段。
県道から国道に昇格したのは1974年(昭和49年)。
両側にあじさいがボリューム豊かに植栽されている。
近くに,"津軽海峡冬景色"の歌謡碑と,"鶴瓶の家族に乾杯"にも登場した名物かーさん。 |
|
|
|
|

|
昇仙橋
荒川
仙娥滝の下流,頭上に張り出した巨岩の下を歩いて近づく。 |

|
静観橋
荒川
土産物屋の集まる仙娥滝入口付近に架かる。 |
富士宮市。富士山本宮浅間大社の大鳥居の近く。 |
2012.04 |
|
 |
神田宮橋
神田川
赤がねの擬宝珠が輝く。
下流側高欄は直線であるのに対し,上流側は彎曲していて非対称なのが面白い。
すぐ近くにお宮横丁があり,B級グルメの富士宮やきそばが有名というがイマイチだった。 |
|
|
 |
弁天橋
平滑川
平滑川河口近くに架かる最下流の橋。
ここから下田港へ向かって100mほど進むとペリー上陸の碑が立つ。 |
 |
霊山橋
平滑川 (ペリーロードとされるこのあたりは"弥治川"とも呼ばれるらしいが,"弥治川"は川の名ではなく,遊郭などがあったかつての町の名であったようだ)
下田条約が締結された了仙寺は,すぐ近く。
橋も寺も,読みはどちらも"りょうせん"。 |
|
|
|
|

|
黒門橋
紅葉谷
|

|
酔月橋
地獄谷
|

|
白鶴橋
?
城址の側からこの橋を渡ると動物たちが迎えてくれる。 |
|
|

|
二の丸橋
二の丸堀
水堀だった二の丸堀だが,かつては電車が走り,現在は遊歩道となっている。 |
|
|

|
桜雲橋
その名の通り,桜の雲間に見え隠れする。 |

|
白兎橋
かつて"白兎"は,"波久止"と書いたのだろう。 |

|
桜小径歩道橋
見上げる。 |

|
白山橋
三峰川(みぶがわ)
桜小径歩道橋の上から望む。 |
|
|
_a1.jpg)
|
神橋
堀
正面から。 |
小田原城址。戦国時代,北条氏の本拠地。
桜は散ってしまってツツジの季節。御感の藤棚も咲き始めていた。天守閣は1960年(昭和35年)に外観復元されたもの。 |
2013.04 |
|

|
小峰橋
箱根口門
御茶壺橋の名で親しまれているという。 |

|
常盤木橋
常盤木門
この橋を渡って天守閣に至る。。 |

|
住吉橋
銅門(あかがねもん)
NPO法人化されたガイド協会の事務所がある。
横から眺める。 |

|
馬出門土橋
馬出門
めがね橋の名もあるらしいが,レンズがひとつだけではどうも…。
真横からの遠景。向こうに重なって"学橋"という赤い橋が見える。 |
鶴岡八幡宮。源頼朝ゆかりの神社。
"八"の字は2羽のハトで描かれている。鳩は神の使いとして武士たちに崇められていたという。鎌倉名物"鳩サブレ"もここから…
ところかわって長野・善光寺山門の額には,5羽の鳩と牛の顔が隠れている。 |
2013.04 |
|

|
太鼓橋
源平池
かつては観光客も自由に歩いて渡れた時期もあったらしいが,現在は赤い柵で閉じられている。
かわりに両側に赤い欄干の橋が架けられている。
そもそも,太鼓橋そのものがもとは朱塗りの木橋で"赤橋"と呼ばれていたそうな。 |
|
|
北上展勝地。北上市立公園展勝地。
角館,弘前と並んで,みちのく三大桜名所のひとつ,ということらしい。
目玉の桜大路は北上川に沿って展開している。
訪れた21日は小雨もばらつくちょうどよい桜曇り。 |
2014.04 |
|

|
葦切橋
?
この橋が架かる川も北上川なのかどうか…?
いかにも小さい川で,名もわからない。
が,この橋,昭和35年竣工というから50年以上の歴史を刻む。 |
弘前城。津軽氏の居城。
天守(現・弘前城資料館)から岩木山を望む。
さくらまつりは,訪れた翌日の23日からとのことだが,まだまだツボミ状態だった。 |
2014.04 |
|

|
下乗橋
内濠
本丸と二の丸の間に架かる。
天守から眺めた下乗橋。 |

|
鷹丘橋
内濠
本丸と北の郭(くるわ)の間に架かる。 |

|
賀田橋 (よしたばし)
二階堰
三の丸と四の丸の間に架かる。
さくらまつりとあって,このあたりには屋台が立ち並ぶ。 |

|
亀甲橋 (かめのこばし)
外濠・北門
橋を渡ると,重要文化財・石場家住宅があり,ここでは地酒が売られている。 |
桧木内川堤。角館。
2km続くという堤の桜のトンネルは,まだ堅いツボミ。
もっぱら武家屋敷群を散策するのみ。 |
2014.04 |
|

|
古城橋
桧木内川
|

|
横町橋
桧木内川
|
銀山温泉。大正浪漫の面影が漂う街並。
というが,どうしても銀山川に架け並べられた橋たちに目がいってしまう。
温泉街の行き止まりの先には雪解けの増水で水飛沫をあげる白銀の滝。 |
2014.04 |
|

|
白銀橋
銀山川
橋のたもとにプレートが。
銀山温泉の湯のまちづくりが,”手づくり郷土賞”を受賞したのだとか。 |
松島・五大堂。五大堂は松島のシンボルなのだそうな。(縁起)
ごく小さな3つの島からなっていて,いずれも朱塗りの3本の木橋によって繋がっている。
最初の橋を除く2つの橋は,いわゆる”すかし橋”。
ここではふたつの鰐口(その1,その2)に接する。
しかし,石狩弁天社の鰐口の響きに比肩するものではない。 |
2014.04 |
|

|
一つ目の橋
松島湾
すかし橋ではない。
横から。 |

|
二つ目の橋
松島湾
すかし橋。
横から。 |

|
三つ目の橋
松島湾
すかし橋。
横から。 |
|
|
兼六園。文化財指定庭園・特別名勝。
今年の桜の開花宣言は例年より早く 3/30。園は無料開放されていてこの日(4/5)すでに満開!。
隣接する金沢城公園には兼六園に向かい合って”石川門”が建ち,”石川橋”も架かっているということを帰宅後に知ったが,後の祭り。 |
2016.04 |
|
 |
雁行橋
曲水
11枚の赤戸室石が橋桁として並べられ,雁が飛行する様を模していることから名づけられた。また亀甲橋とも呼ばれる。石の摩耗が著しく,現在は歩行禁止。
快晴。逆光でデジカメのレンズの汚れが目立つ。対岸から撮る。
曲水は,1600年代前半に造られた防火用水「辰巳用水」を利用している。 |
白川郷。世界文化遺産。
合掌造りが集まる荻町集落へは観光車両の進入は規制されている。
左岸,観光案内所。右岸,神田家住宅,長瀬家内部。 |
2016.04 |
|
 |
であい橋
庄川
観光バスの駐車場と荻町集落との間を隔てる庄川に架かる人道橋。
不思議な橋だ。コンクリート床板で長さ 107m もあるのに橋脚は1本もない。
床板の中にメインケーブルが通っているという,らしからぬ吊り橋なのである。
左岸からの眺め ①,②。 |
飛騨高山。(2度目)
宮川 (富山県では神通川) の左岸に,古い町並み(伝統的構造物保存地区)。
右岸に,飛騨国におかれた江戸幕府直轄の代官所・高山陣屋(国史跡)。
|
2016.04 |
|
_c1.jpg) |
中橋
宮川
右岸下流側の橋のたもとには立派な桜の木。残念ながらようやくチラホラ花が開いたばかり。
左岸上流側の橋のたもとには,飛騨の匠の像が立つ。 |
輪島。能登半島。
輪島塗伝統工芸と,三大朝市のひとつの輪島朝市などで有名。
2015年,NHK連続テレビドラマ「まれ」の舞台になった。
さらに,旧厚田村(石狩市と合併)と旧門前町(輪島市と合併)とが北前船交易によるつながりから長年交流してきたことを踏まえて,現在,輪島市は石狩市の友好都市である。 |
2016.04 |
|
 |
いろは橋
河原田川
あいにく小雨降る中での輪島朝市。
早々に切り上げての帰り道,目に飛び込んできた赤い曲弦トラス。
あとで分かったのだが,「まれ」ではしきりに登場したらしい。
親柱,斜め横から。 |
山中温泉。加賀温泉郷のひとつ。
こおろぎ橋のあたりから下流1kmくらいの間は鶴仙渓(かくせんけい)と呼ばれる美しい渓谷の景勝地で遊歩道が整備されているという。 |
2016.04 |
|
 |
こおろぎ橋
大聖寺川(だいじょうじがわ)
元禄時代に架けられたという総檜造りの人道橋 (現橋は平成2年架橋)。
この橋も,”手づくり郷土賞”受賞。
左岸から,右岸から,下から,渓流とともに。
山中温泉のシンボル的存在。1978年,TBS系でドラマ化された。 |
永平寺。曹洞宗大本山。
2本の石柱「杓底一残水」「流汲千億人」が立つ正門から続く参道の右を永平寺川が流れる。
なお,正門の外に「本山元標」という石柱が立つ。元標マニアとしてはおおいに気になる。 |
2016.04 |
|
 |
偃月橋(えんげつきょう)
永平寺川 (九頭竜川支流)
反って曲がった半月にも似ている様から”偃月橋”と名付けられたという。
現在の橋はコンクリート製 (昭和43年改修)。
渡るとすぐに,湧泉稲荷のほか,いくつかの祠が建つ。
左岸からの眺め ①,②。 |
|
|
大宰府天満宮。菅原道真(天神さま)を祀る。
知る人ぞ知る,「学問」の神様である。本殿。
参道の突き当りに寝そべる御神牛が可愛い。 |
2017.04 |
|
 |
三つつながった神橋
心字池
心字池は,「心」という漢字をかたどった池。
同名の池は,大宰府だけでなく国内各地の日本庭園で設置されているらしい。
太宰府天満宮の心字池は,参道の行き止まりから左折し鳥居をくぐるとすぐにあって,池には三つの赤い橋 -太鼓橋-平橋-太鼓橋- が架けられている。
橋は順に「過去」「現在」「未来」を意味づけられていて,橋の上ではそれぞれ,"振り返ったり","立ち止まったり","つまづいたり"してはいけないとされる。
写真を撮るのに夢中で,「過去」の上では振り返り,「現在」の上では立ち止まり,もはや「未来」はないので幸いにもつまづくことはなかったとはいえ,身は清められなかったに違いない。
左の写真は,上から,「過去」「現在」「未来」。
|
 |
 |
|
|
 |
高千穂三代橋 [前回の高千穂三代橋]
五ヶ瀬川
高千穂峡に架かる3つのアーチ橋を同時に捉える。
新しい(=大きい)方から順に,神都高千穂大橋(左の写真では真ん中),高千穂大橋(左の写真では一番上),神橋(左の写真では一番下)。 |
 |
槍飛橋
五ヶ瀬川
|
 |
御橋
五ヶ瀬川
|
青島。(2度目)
青島神社の神門扁額には"鴨就宮"とある。鴨が飛来することから鴨就島とも呼ばれていたからだとか。
天の平瓮(あめのひらか)投げを試みる(1枚200円)も,ぽとりと足元近くに落ちて割れもせず。願いは叶いそうもない。 |
2017.04 |
|
 |
弥生橋 [前回の弥生橋]
鬼の洗濯岩
正面から見た弥生橋。
潮が引いているようで,前回に比べると鬼の洗濯岩もかなり露出している。
が調子に乗って波打際まで進むと,岩には海苔状の海藻が付着していてつるつる。あわやスッテンコロリンとごつごつ岩に体を打ち付けるところだった。 |
桜島。
ご覧のとおり,今回の橋はあらかた赤い神橋。旅行会社の忙しいツアーではいたしかたのないところだが,でもそればかりではつまらない。
というわけで加えたのが車窓からのこの橋。
バスに乗ったまま渡る橋の写真を撮るのはとてもとても難しい。 |
2017.04 |
|
 |
牛根大橋
錦江湾
垂水市牛根と桜島との間に架かるアーチ橋。全長381m。
アプローチがかなりカーブしているので,うまい具合に車窓から撮ることができた。 |
|
|
 |
禊橋
蓮池
比較的珍しい3連のアーチ橋。おりしも桜が満開。
かたわらに不思議な生き物が・・・"きじ馬"というのだそうな。東北の"こけし"と並んで九州(人吉地方を中心に)の伝統的な木製玩具ということである。 |
|
|
 |
神橋
錦波川
境内への正面入り口に架かる。
錦波川にはホタルが飛び交うという。
境内の対岸に祐徳博物館がある。 |
 |
太鼓橋
神池
楼門の手前,鯉の泳ぐ神池に架かる。 |
|
|
宮島・厳島神社。(2度目) 宮島は日本三景&世界遺産。
厳島神社は市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)を祀る社殿として創建された。
古くは「伊都岐島神社」。市杵島姫命は神仏習合時代に弁財天と同一視されていた。
隣接する大願寺は日本三大弁財天のひとつである。
シンボルともいえる大鳥居はかなり色が褪せてきている。
観光客は外国人の方が多いのかもしれない。 |
2018.04 |
|
 |
反(そり)橋
重要文化財の木造橋の中でも最古の橋という。
現在は立入禁止で使われていない。
全長24m。能舞台正面の廻廊の角に位置する。 |
 |
筋違(すじかい)橋
紅葉谷(御手洗)川
金色の擬宝珠と赤い手すりが特徴的。
なぜか川に斜めに架かっている。 |
秋芳洞。(2度目) 特別天然記念物の鍾乳洞。
同じく特別天然記念物のカルスト台地・秋吉台に隣接。
鍾乳洞の観光コースは約1km,上りコースと下りコースがあるが,いつも下りコース(^^;。 |
2018.04 |
|
 |
滝穴橋
鍾乳洞から流れ出る川
鍾乳洞正面(上りコース)入口に架かる。 |
角島。日本海周防灘に浮かぶ。
島のシンボル・角島灯台は1876(明治9)年初点の石造灯台。
内部が一般公開されていて上がることも可能(だが,事情があって果たせなかった,残念)。 |
2018.04 |
|

展望台から |
角島大橋
日本海
2000(平成12)年完成のPC箱桁橋。(航路部242mは鋼床板箱桁)
全長1780m,幅員6.5m。
自然景観を壊さないようにとの設計理念に基づく。船舶が通過する航路部を除いては橋脚は低い。
本土側入口に海士ケ瀬(あまがせ)公園が整備され,展望台があって角島を一望できる。 |

a |

b |

c |
|
(a) ホテル西長門リゾート裏手の浜辺から
(b) 橋のたもと,南側から
(c) 北側から |
|
岩国・錦帯橋。(2度目) 岩国は藩主・吉川家の城下町。
山頂の岩国城は1962(昭和37)年に再建されたもの。
今回はやや時間があったのでロープウエーを利用,天守閣の展望台まで上がった。 |
2018.04 |
|

岩国城天守閣から |
錦帯橋 [前回の錦帯橋]
錦川
岩国城と城下町をつないで1673(延宝元)年創建の木造5連のアーチ橋。橋台,橋脚は石垣。
全長193.3m,幅員5.0m。
錦帯橋往復\300. ロープウエー往復\550. 岩国城\260. |

a |

b |

c |

d |

e |
|
(a) 上流の錦城橋から(車窓)
(b) 左岸下流,川にせりだした州から
(c) 右岸,川原から
(d) 左岸,堤防上から
(e) 左岸,橋の下から |
|
|
|
(Topics) |
明石海峡。 淡路島(淡路市)と兵庫県明石市との間の海峡。
もっとも狭い所で幅3.6km。
明石港:右舷灯台,左舷灯台; 岩屋港:右舷灯台,左舷灯台 |
2019.04 |
|
 |
明石海峡大橋 (神戸淡路鳴門自動車道)
明石海峡
世界最長の吊り橋とされる(自動車専用道路)。全長 3911m。
明石港(明石市)と岩屋港(淡路市)との間に運航されている淡路ジェノバラインに乗船,橋の下を潜り抜ける。帰りは観光バスで橋の上を走って往復。 |
|
|
姫路城。 (白鷺城とも) 世界文化遺産・国宝
大天守保存修理工事は約5年がかりで 2015(平成27)年終了。
天守閣最上階(六階)まで上がると息が切れる。入城料 大人\1000. |
2019.04 |
|
 |
桜門橋
大手門の前の内濠
江戸時代の木橋をイメージして架けられた。2007(平成17)年完成。 |
京都・嵐山。 一帯は史跡・名勝。
桜や紅葉の名所。
なにはともあれ,日本人,外国人入り乱れてヒトの多いのに呆れる。自分もまたそのひとり。
貸衣装やさんがおお流行り。橋の写真を撮るのも決死の覚悟。 |
2019.04 |
|

中洲・上流側から |
渡月橋
大堰川 (渡月橋の下流では桂川。上流の方では大堰川だったり保津川だったり混線模様)
左岸から嵐山公園のある中洲に架かる。
9世紀(平安末期)に架橋されたのが始まりという。1606年現在の場所に。
現橋は1932(昭和7)年,橋脚をコンクリートとして架設。高欄のみ木製。長さ 155m。
中洲・下流側から,左岸・下流側から |
湯浅町。(和歌山県) 熊野古道に接する。
金山寺味噌の製造過程から醤油が生まれた町といわれる。 |
2019.04 |
|
 |
新北栄橋
山田川
新北栄橋自体は1980(昭和55)年架設の比較的新しい普通の橋。醤油醸造業を中心に発展した町並みが残された伝統的建造物群保存地区を地元のガイドさんに案内される。 |










_a1.jpg)
















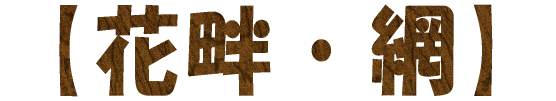






_a1.jpg)




_a1.jpg)

_a1.jpg)
































_c1.jpg)




































