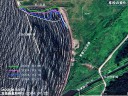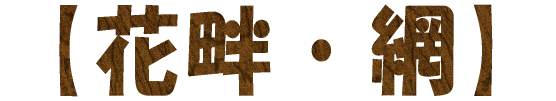| 2024.12.31版 |
|
ありがとうございました,の巻 |

a |

b |

c |

d |

e |

f |
|
2024年,今年も大晦日まで今際の際(しつこい)の【花畔・網】にお付き合いいただいた皆様,ありがとうございました。おかげ様であと数時間で2025年を迎えることができそうです。
お礼の気持ちをこめて,またまた12/21の画像です。
(a) 石狩川の氷の上に君臨。この時期にはよく見かけるオジロワシ,かと思いましたが,尾ではなく肩が白くて変だ。オオワシでした。
(b) 川面では漁。背後から高さ400mそこそこの阿蘇岩山が見下ろす。
(c) 蓮の葉氷にはまだ未熟。
(d) ドラゴンに替わって最近注目している巨大流木。最初に出会ったのが10/29(だと思う)。ここらへんでうろうろする流木たちと同様,彼もその後2ヶ月間位置をずらし続けている。
(e) 砂嘴先端近くから見た石狩新港。煙を吐いているのはLNG火力。右に浮いているのは船。寒かった。
(f) 12/27版にも書きましたが,(C)部の侵食の爪痕。(F)部でもこんな具合。削った大量の砂を奇麗に持ち去る離岸流は凄い。
また,あした。 |

a |

b |

c |

d |

e |

f |
|
昨日(12/27),句会でした。当日の幹事から席題というものが出されます。通常漢字一文字で,その一文字を組み込んだ俳句をほぼ30分以内に作らなければなりません。昨日出されたお題は『今』。ありふれた文字ですからいくらでもできそうですが,実は意外と難しい。
スマホで『今』を使った熟語や慣用句を調べます。やたら沢山あります。全部見るだけでも時間が刻々と経ってしまいます。そんな中,ふと目にとまったのが「今際の際」。へぇー,「いまわのきわ」って,漢字ではこう書くのかぁー。いまわのきわ間近のお爺さんにして,初めて知った漢字でした。なら,これを使わないわけにはいかないべさ。無理して作った結果,参加者による鑑賞点では零点でした。ほとんど死にそうです。まさしく今際の際にあります。
それはそうと,気を取り直します。12/21の浜歩きで最も気になったのは,昨日書いた海側汀線の凹凸,です。凹部における浜崖の侵食がどこまで進むのか予断を許しませんが,ここではその他のいくつかを。
● ドラゴンの頑張っているあたり,昨日のGPS全体図でもかなり膨らんでいます。11/8版の地形変化で見たのと同じ定点観察点から眺めた画像が(a)です。その4日後の12/25,八幡堤防から11/29版と同じ角度で眺めた画像が(b)です。川側へ地形が膨らんだのは11月下旬以前だったようです。
● 岸辺の氷。川岸では(c),海岸では(d)。どちらも奇麗ですが,私が注目するミラクルアイスは海岸で見られます。
● (e) 昨日も書きましたが,なんとなく転がり落ちたそうなマウニ脇の土のうの今際です。11/27版の続編です。
● (f) そして今年も真冬の無辜の民。殺戮はいつまで続くのだろうか。いまわのきわに,重たい話は書きたくないのだが。 |

GPS全体図 |

A |

B |

C |

D |

E |
|

F |

G |

H |
|
|
|
|
遅ればせながら,12/21(ポンプ小屋起点),左岸砂嘴浜歩きで気になった兆候のひとつである。
GPS全体図をご覧いただければ分かることなのだが,前回9/6(この日はヴィジターセンター駐車場起点)の軌跡に比べて汀線軌跡がかなり大きく波打っていることが見て取れる。歩いた区間で少なくとも8ヶ所で汀線の凹部が確認される。図中のこれらの箇所に便宜的にA~Hの番号を振り,上の画像A~Hに対比させた。近頃これほど汀線の凹凸が見られるのも珍しいし,この傾向がさらに強まると凹部において浜崖まで侵食されかねないので今後の動きを注視する必要があるだろう。とりわけ,B部(中道の行き止まりよりやや南),C部,F部(ヴィジターセンター間近)においては危険信号である。
さらにG部・マウニ脇においては,凹部が土のうが積まれたあたりよりやや北側であることが救いだが,予断は許されない。 |

a |

b |

c |

d |
|
油断していた。昨日(12/24)は石狩でも大雪。アメダス公式では石狩(生振)の降雪量は24cmとのことだが,花川北では間違いなく40cm以上。午後9時近くまで雪かき。やや不機嫌だったかもしれないと反省する。
今朝,新たな積雪はほんのちょっぴり。しかし除雪車の置き土産がてんこもり。参った。けど参らない。6時15分ころから1時間半ほどたっぷり汗を掻く。おかげで血圧も,192-83から150-74へ。そして,かねて予約の歯医者へ往復。
ほとほとくたびれたので後は寝ていたかったのだが,お天気がそれを許してくれない。12月,昨日まで酷い天気続きだったのになにを間違えたのかとんでもなくよい天気。こんな日をみすみす見逃してはいられないお爺さんは,これが今年最後になるだろうと右岸へ。もちろん車の走行は不能なので,衛生センター角に駐車して,カンジキを履く。
だれ一人歩いた跡のない道(a)をズッポズッポ歩く。意外とカンジキの調子がいい。振り返って衛生センターを望む(b)。すがすがしい
やがて市道からから外れて浜へのけものみちに降りていく(c)。絶好調。
荒れ続きだったので気になっていた堆砂の寄り付きは12/10からほとんど変わっていないことが確かめられた。ここ数年冬季には必ず侵食され続けてきたこの浜にも,新たな展開が定着しようとしているのかもしれない。
(d)は,崖の上の定点観察点Tbからの眺めである。お爺さんのカンジキの足跡が,あの世へ向かって迷うことなく連綿と延びていることを物語っている。カラスには笑われたが。 |
今日は句会でした。予想通り惨憺たる結果でしたので,多くを語りません。
今日は,新しいパソコンをいかに手なずけてきたかのまとめ,です。調べてみると,2年前2022年発売のDELLの安売り製品でした。あって然るべきものが装備されていません。CD/DVDドライブ,LANポート,そして,大容量記憶装置が220GBと決定的に物足りない(私が1年間に撮る画像がそれだけで150GB近くになる)。
ので,買い足したのが
① 外付けCD/DVDドライブ
② LAN-USB変換アダプタ
③ HDD-USB変換アダプタ
①②は
12/10版にも既に書きましたが,③は廃棄するパソコンの750GB内臓HDDを取り外してこれからも使用せんとするためのもの。それらを合わせても8000円に満たない額ですから,今回のパソコン関連出費は9万円未満に止めることができました。
それにしても12月は岩見沢のような豪雪は免れていますが,荒れ続き。右岸にも2日と10日に行ったきり。左岸砂嘴は先月12日以来ご無沙汰。そんな中昨日は無風快晴。でも猛烈寒かったです。合計1万歩を越しました。それよりなにより,直近30日間平均歩数が6000歩を越しました。メンドクサクなったのでまた明日。
| 2024.12.21版 |
|
新パソコンでの初仕事,の巻 |
 |
 |
|
やれやれ,どうにかやっと新しいパソコンで書き込みができました。
今日,ほぼ40日ぶりの浜歩き。とってもお天気はよかったけれど,寒かった。最後にはカンジキとの苦闘。息も絶え絶え。
でも,先端でミラクルアイスに遭遇。おみやげです。見ていた人にいわせると,作為的な構図,らしいです。しかたないでしょっ。
いろいろ書こうと思っても操作が馴染みません。明日は句会。俳句もできていないのでおやすみなさい。 |
根雪とは,降って積もった雪が春までずっと地面を覆い続けることなのだろうけれど,根雪の初日をどこにするかは意外と難しい。気象庁の用語では根雪のことを「長期積雪」というらしいが,積雪がある程度継続しても気が変わっていったん融けて,そしてまた積もったなんて場合の取り扱いがメンドクサイ。なので,ここでは積雪がいったんゼロになったらリセットしてしまうことにすると,石狩の今年の根雪初日は12/5ということになりそうだ。といってもこれから春まで融けないことを前提としてだけれど。
2023年は12/12(4/7),2022年は11/30(3/27),2021年は12/8(4/11)。[ここで,()の中は最終根雪日]。近年では2021~2022年の冬がドカ雪で,2022~2023年の冬はラクチンだった。ので根雪初日でその後の冬を占うのは早計である。
雪かき爺さんの雪かき開始時刻は朝6時45分ころである。昨日(12/12)は80分ほど,今朝は50分ほど大汗を掻いた。血圧は,昨日は雪かき前178-80雪かき後145-72,今日は雪かき前185-83雪かき後140-63。雪かきは血圧を下げる。
Topicsもすっかりサボり癖がついてしまった。そろそろ
雪のページも始めたいところなのだが手が回らない。雪かきもさることながら,新しいパソコンの設定に悪戦苦闘。なんとか今ある3台のパソコン間でのネットワーク接続(ファイルの共有)が可能になった。これで作業が進めば11年目のトロくさいパソコンも廃棄できる。とかなんとか今これを書いているのはその古いパソコン。これが思いがけずにスラスラ動く。彼も生き残りをかけた戦いに打って出たのだろうか。わからないものだ。
| 2024.12.10版 |
|
冬になっても堆砂頑張る,の巻 |

a (12/2) |

b (12/10) |
|
第二突堤近くへの堆砂の寄り付きについては11/26に追補の形で報告して以来となる。
その後は12/2,五の沢林道に行く前に立ち寄って変わり映えしないヤッチャだなぁと,無視してやった。
その翌日から海は荒れた。さすがのお爺さんも12/9まで,その後どうなったのかをなんとか辛抱した。
今日(12/10)は依然として西高東低で荒れ気味とはいえ,ヨドバシカメラに行ったついでに走った。
けれど,上の画像を見て分かるように,一部白くはなっているが堆砂の寄り付きにはさほどの変化は見られなかった。
だからここでは,なぜヨドバシカメラに行ったか。。。
11年使い続けている作業用のパソコン(実は今現在もそれを相手に苦戦している)がどうにも我慢できなくなった。しかも機能的にWindows 11 に移行することも不能だという。
一昨日(11/8),イトーヨーカドーが去った後の CiiNA CiiNA 屯田 2階のコジマのチラシに誘われて行ったのが運の尽き。安売りの目玉の
DELL のパソコン(8万円以下)を買ってしまった。しかし。。。あぁそうか。安いだけにアレもないしコレもない。
というわけで,ヨドバシカメラに外付けCD/DVDドライブとLAN-USB変換アダプタを買いに行ったというわけだ。
パソコンといえば,生まれて初めて買ったのは1983年のNEC PC-8801。いくらしたと思いますか?本体と,モニタと,フロッピーディスクドライブと,プリンタと,合わせて61万5千円でした。バブル崩壊前とはいえ・・・
そして今回買ったのがもしかしたら14台めくらいになりますね。絶対にこれで最後にしますからお許しください。 |

11/26 6:54 |

12/02 7:00 |

12/06 6:53 |

12/06 6:53 |

12/06 6:57 |
|
最近拝んだ石狩(といっても,わが家の2階のベランダから)の朝陽。日出時刻はまだ少しずつ遅くなり,だから朝陽が昇る位置もちょっとずつ南にずれていく。
というよりなにより,今朝は冷えた。石狩の最低気温はこの冬もっとも低いマイナス5.8℃。しかも朝陽が昇り始める6時50分前後。
朝焼けの空にくっきりとサンピラー(太陽柱)が確認できた。そして3,4分後には消えてなくなり,一転曇って朝陽も顔を隠してしまった。 |

五の沢ダム |

高富ダム |

八の沢鉱業所跡 |

八の沢油田跡 |

伊夜日子神社跡 |
|
久しぶりによい天気。お誂え向きの高気圧なか゜ら,ややひ弱。懲りずに石狩川右岸・突堤遺構を眺めに行くも,浜辺のクルミ以外に得るものなし。久しぶりに海から山へ矛先を替えました。当然,鈴,笛,持参です。
農業用水用の貯水池・五の沢,高富ダム。かなり水が抜かれていましたが,まだまだです。五の沢ダムは16番取水孔が開けられていました(一番下は18番)が,水面には薄氷。高富ダムでは堤頂に近づくといっせいに鳥たちが逃げていきました。
五の沢ダムに通ずる林道はまだゲートが開いていたのでさらに進入。ほとんど久しぶりの雪道。鉱業所跡,油田跡,伊夜日子神社跡などを半年ぶりに眺めて感慨にふけってきました。
本当は望来ダムまで行きたかったのですが,クマの現実味が高まるのでやめました。 |

A (6/21) |

A (11/26) |
_241013_thumb.jpg)
B (10/13) |
_241126_thumb.jpg)
B (11/26) |
|
ドラゴンは昨年末以来安住の地を得て動かない。動かなければ,あまり面白くもない。ということで,今年の Topics では取り上げる回数がめっきり減ってしまった。もしかしたら今年最後になるかもしれないが,ドラゴンの近況ということで 11/26 のドラゴンの画像をここに貼り付けたい。いずれも石狩川右岸の定点からの遠望で,A は八幡堤防から,B は知津狩新橋からである。どちらもちょっとした比較のために少し前の画像も付け加えてある。
A : 石狩川左岸のドラゴンが居座る辺りから石狩川のやや上流方向は,11/8版で書いたように堆砂の寄り付きにより地形が安定しない。6/21に比べて11/26ではドラゴンの右側に川岸が大きく膨らみ出ていることがよく分かる。
背後の右遠方で伸び出しているのは河口導流堤。手前側には川の増水時に流されてきた流木類が右岸の水制工による浅瀬に引っかかっている。
関連画像 : 1/1 , 3/8 , 3/27 , 4/4 , 4/11 , 4/18 , 4/24 , 4/30 , 5/11 , 5/18
B : 背後の建物はマウニの丘。11/26の屋根の上に突っ立っている風車は,今年の秋中央埠頭近くに建てられたもの(12/1 画像追加)で,いま現在石狩で一番新しい。10/13の画像では風車建設中のクレーンが見える。
ドラゴンは川岸から結構離れた砂の中に胴体を埋めているので,しばらくは安泰に違いない。
関連画像 : 4/7 , 7/20 , 7/25 |

4/23 |

6/7 |

8/15 |

11/26 |
|
市道灯台線・マウニの丘脇。私がずっと気になっているところである。
幸いこの数年,少なくともあそびーち以北では(砂嘴先端部を除いて)大規模な浜崖の浸食/崩落は認められず,この部分もとりあえず安泰である。
今年の4月以降,昨日(11/26)まで,並べられている土のうのほぼ同じ部分の様子を外側(海側)から眺めた画像を並べてみた。
杞憂かもしれないが,画像の右から6番目の土のうが転がり落ちたがっているようにも見える。転がり落ちても,車道側には影響はないのかもしれないが・・・
11/13b版で触れたはまなすの丘公園の木道改修工事。終わっていた。すっきりと。 |
| 2024.11.25版 |
|
第一突堤へこたれず,の巻 |
|
11/17版に続く |
|
11/26 追補 |

A (11/20) |

B (11/20) |
|

C (11/16) |

D (11/20) |

E (11/26) |
|
第一突堤がへこたれないのか,お爺さんがへこたれないのか,どっちか分からない。けど,誰ひとり気にも留めないことにこだわり続けるお爺さんなのである。リスと遊んでいるばかりの呑気なお爺さんと思われるとシャクである。
いろいろあって5日も経ってしまったが,11/20のこと。11/16に続いて石狩川河口右岸。大潮は過ぎたがこの日も高気圧下。2,3日海は荒れた後だったが行ってみる。第一突堤,顔を出すかっ!?
出したっ!
しかし,ずっと出ているわけではない。波の間にまに顔を出したり引っ込んだり(A)。おまけに沖合側にも新たにいくつかの頭が見え隠れ(B)。
10/25版に続いて,この両日確認した時間帯での石狩新港潮位は,11/16,および11/20。どちらもマイナス5~10cm。情けない。
しかし違いは海の荒れ方。普通なら波は静かな方がいいに決まっているが,実はそうでもない。11/14から11/20までの石狩湾新港有義波実況グラフを見ると,観察時の有義波高は11/16に比べて11/20の方が荒れている分だけ2倍近く大きい。波の上がり下がりの幅が大きいのだ。結果的に,第一突堤の頭がずっと見えているわけではないが,見えた時には大きく見える(A)。しかもおまけに11/16には見えなかった沖合の木杭までチラッと姿を現わしてくれたのだった(B)。
また,11/13a版に続いて,定点観察点Tbから望む第二突堤寄り付き堆砂の動きにも注目したい。
C(11/16)とD(11/20)の間に海は荒れた。それを物語るように,Dでは洗われた浜がとても綺麗だ。しかも広がっている。
この傾向がいつまで続くのか目を離せない。例年真冬には浸食されるのが決まりなのだ。ぞくぞくする。
俳句なんて考えていられるわけがない。
【11/26 追補】 さらに今日(11/26)も現地へ。波はほとんどなかったが,潮位は0cm前後。さすがに第一突堤はまったく確認できなかった。第二突堤寄り付き堆砂にはやや離れた沖合に筋砂州状の浅瀬が長く伸びている(E)。当然その浅瀬に渡ることを試みたが,長靴の高さ以上の深さがありそうで,泣く泣く諦めた。 |

i (10/22) |

h1 (10:16:32) |

h2 (10:17:30) |

h3 (10:17:32) |

h4 (10:17:36) |

h5 (10:17:38) |
|
またまたしつこくエゾリスでゴメンナサイ。一度嵌まったら,もがけばもがくほど抜けられなくなるお爺さん,なのです。
(i) 昨日(10/22)のことです。クルミの脇に転がっていたドングリを拾い上げてみると,,,あ,怪しい。。。これはもしかしたら,いやきっと,リスが遺した歯型ではないだろうかっ!
(h) そこで前回(11/15)現れた時の画像を入念にチェックしてみました。()内の数字はここでは撮影時刻で,何秒までは正確な時刻を保証するものではありませんが,リスがどのくらいの敏捷さで動いているかを察知することができるでしょう。
リスは現れてはクルミを咥えて去り,そしてまた現れるを4,5回繰り返しました。
(h2-5) がドングリとの格闘編。そのひとコマ先が(h1)で,2秒後にクルミを咥えて立ち去りました。この画像の←のドングリを注目してください。
56秒後にまた現れたかと思うと間髪入れず咥えたのがドングリだったようです(h2)。(h1)のドングリはなくなって,咥えられています。
その2秒後の画像を拡大(h3)。長く鋭いノミのような前歯で割ろうとしています。
2,3秒そのドングリと闘っていましたが,美味しくなかったとみえて別なドングリに目をつけニオイを嗅いでいます(h4)。
しかしドングリはやはり気に食わなかったのでしょう,すぐに近くのクルミを咥えました。それが11/21版の(e-2)で即座にすっ飛んでいきました(h5)。見ると最初に噛みついたドングリが残されていることが分かります。
(i) のドングリはこのドングリに間違いないでしょう。リスには,ドングリよりクルミ,なのでしょうね。
ついでに,クルミやドングリの中に,プラタナス(鈴懸の木)の実も紛れ込ませておきました。どうやらこれにも齧られた痕跡が。でもこれはいかにも美味しくなさそう。 |

e - 1 |

e - 2 (10:17:38) |

e - 3 |

f |

g - 1 |

g - 2 |
|
(e) 11/14版の後,実はその翌日11/15にもエゾリスはいろいろな表情を愉しませてくれた。けど,その後杳として姿を見せない。
なにしろ11/18から3日間ほど庭も白くなった。
(f) 11/19,それでも果敢にアタックする足跡。カラスだ。エゾリスよりよほど頭がよいのかもしれない。
(g) 今日(11/21)つまらないから,ふと思いついてエゾリスたちの素行を確かめてみた。11/14版の(d)で獲物を隠して安心している姿があったところだ。落葉をよけてみると,あっけなくその下に隠されたクルミ?が発見された。うーむごめんね,また落葉を被せて隠しておいた。
でも,この所在を彼はしっかりと覚えているのだろうか。だとしたら私は躊躇なく帽子を脱ぐ。ゴメンナサイ。 |
| 2024.11.17版 |
|
こ,これはねぇ。。。,の巻 |
|
第一突堤の頭 |

A (10/21) |

B (11/16) |

C (11/16 拡大) |
|

D (10/9) |

E (11/16) |
|
昨日(11/16)は満月。ということは干満の差が大きくなる大潮。そこへ高気圧がどっかり乗っかってくれればさらに海面が押し下げられて潮位が下がる。潮位が思い切り下がると,再び三度第一突堤がひょっこり顔を出す。と,大いに期待した昨日だったが,肝心の高気圧が弱々し過ぎた。先月第一突堤が現れた10/21の観察時の潮位(あくまでも,港湾局により新港東埠頭に設置された潮位計によるもので,石狩川河口右岸の潮位とイコールとは云い切れない)はマイナス20~25cm(東京湾平均海面を基準として)。一方昨日(11/16)観察時の潮位はマイナス5~10cm。15cmくらい負けている(高い)。結構目を凝らしたつもりだったが,第一突堤の頭を認めることができなかった。
しかしパソコン画面でおもむろに撮影画像を睨みつける。第二突堤寄り付き堆砂の定点観察点Tbから首を振って第三突堤方向を眺めた画像,A及びB。A(10/21)には右側にくっきりと第一突堤も写っている(赤楕円)。B(11/16)ではどうか?な,なんだか赤楕円の中はあやしい。さらに拡大して見たのがC。間違いない。水制の木杭が1ヶだけ海面から頭を覗かせている!しかしさすがにこれは肉眼では無理だっ。
いまさらながらの蛇足
最近凝っている突堤(第一,二,三)はいずれも河口導流堤(1959年着工)の付随工作物。第二突堤だけは導流堤の基部としてテトラポットを主体に頑強に構成されているけど,第一,第三は浸食から導流堤を護るための木杭(一部コンクリート)主体の水制工で脆弱。私同様余命いくばくもない。
知津狩川河口と聚富川河口との間にそれらよりも古い1957年施工の第四号水制の遺構がある。これも木杭の構造であるが,浸食を免れいまだに陸続きとして残存している。DとEに,10/9と11/16の雄姿?を示す。砂の堆積/浸食状況そして潮位によって,かなり姿を変える。例えば同じように歩いた7/31にはまったく確認できなかった。 |

5:41 |

6:00 |

6:37 |

6:40 |
|
西の空に満月が沈んでいきました。
およそ30分後,東の空には朝陽が。
それだけのことですけど,なにか?
満月といえば,大潮。朝陽ということならもしかしたら高気圧。潮位が下がるぞっ!
右岸向けて突っ走りました。けど(●´ω`●) また明日。 |

a-1 |

a-2 |

a-3 |

b-1 |

b-2 |

b-3 |
|

c-1 |

c-2 |

c-3 |

d-1 |

d-2 |

d-3 |
|
クルミがしょっぱくて美味しくないからもう来ないのかと思っていたら,今朝またいきなり現れてくれた。嬉しい。
(a)は,ゲットしたらそれを咥えて素早く逃げて行った。けれど,(b),(c)になると徐々に余裕を見せつつある。
最後の(d)は,明らかに獲物を隠してひと安心しているような素振りだ。
結局,ドングリと,その袴ばかりが残ってしまう。クマと違ってドングリを食べる風習はないらしい。
好天の今日,またまた右岸の浜に行ったお爺さんは,クルミを拾ってきたのだった。しかしこういうのって,いいのかどうかわからない。 |

a-1 |

a-2 |

b |

c |
|
(a) 10/31b版で書きましたエゾリス,その後杳として現れません。浜で拾ってきたクルミが余程美味しくなかったのでしょうか。それにしては,転がしておいたクルミがかなり減ってきています。どうやら犯人はカラスたちのようです。用心深くやってきて,咥えて飛び去ります。電線に止まったかと思うと,下の舗装路にぽとっと落とします。また,息の合った車が通りかかり,クルミを踏んずけて粉々にしていきます。ゴチソウサンと叫ぶカラスの声が聞こえるようです。
(b) 昨日(11/12)は石狩浜左岸砂嘴を歩いてきました。はまなすの丘公園の木道が工事中で通行禁止でした。かなり痛んでいましたからね。工期は来年2/5まで,とのこと。それに伴って,砂嘴先端方向へは堤防上を歩くことになります。その先の木道は冬枯れながら気持ちよく歩行可能。
【11/17 追補】11/16立ち寄ると新たな工事標識が。それによると工期は12/10まで,とのこと。どっちが正しいの?
(c) 11/8版に書きました石狩川河口左岸の定点観察点から昨日も撮った画像です。10/29の画像と2週間経て寸分の狂いもないほど変わりません。堆砂の寄り付きによる地形変化でも,右岸第二突堤近辺と左岸河口とでは変化のスパンがかなり異なっていることが分かります。こちら側は少なくとも半年周期で考えてもよさそうです。 |
| 2024.11.13a版 |
|
右岸・第二突堤堆砂の動き,の巻 |
|
10/23版につづく |

2024.10.21 |

2024.10.26 |

2024.10.30 |

2024.11.03 |

2024.11.06 |

2024.11.10 |
|

GPS軌跡 |
上6枚は,定点観察点Tbから。
左は,10/21と11/10の汀線軌跡。
10/23版A図参照 |
|
その後,10/21から11/10までの堆砂の動きを,3~5日おきに崖の上の定点観察点Tb点から追って見た。
ご覧になって明らかなように,堆砂は第二突堤先端側から手前の浜側へと移動してきている。それはGPS軌跡図からも読みとれる。
ただしここで注意すべきは,観察時の潮位である。石狩湾潮位でみると,10/21は-25cmと突出して低く,その次には11/10の+5cm,それ以外はすべて+10~20cm。遠浅の波打際で30cmも潮位が低かった10/21には,他の日の汀線より20m以上も沖合に膨らんで歩くこともできたということも示している。海水をたっぷり含んだ砂は液状化している可能性もあるのでやや怖ろしい。かつて液状化した砂に足を取られて転倒し,高価な?カメラを燃えないゴミとしていまった前科者なのにまだ懲りない。
それはともかくこの週末からの数日,日中の潮位が数センチ(天文潮位)まで下がる。さらに高気圧に覆われるという好条件が重なると10/21に劣らない低潮位が期待される。第一突堤がまたまた頭を覗かせるなど,見逃せない。 |
| 2024.11.08版 |
|
石狩川河口左岸の地形変化,の巻 |
|
9/21版(右岸)につづく |
| 11/8に更新したにも拘わらず,11/7版としてアップしてしまいました。訂正させていただきます。 |

2017.10.25 |

2018.09.20 |

2020.06.13 |

2021.07.19 |

2023.04.22 |

2024.07.22 |
|

2021.10.26 |

2022.10.26 |

2023.10.23 |

2024.10.29 |
上の6枚は Google Earth の背景過去画像である。つまり,再びヒトのフンドシね。
左の4枚は,そこに示されている定点観察点から,衛生センターのある北東方向を眺望した画像である。 |
|
河口の地形変化といえば,近ごろはもっぱら右岸が興味の対象となっている。とりわけ9月の半ば以降から始まったと思われる第二突堤への堆砂の寄り付きから目が離せない。10/21までの動きは報告済みだが,その後も10/26,30,11/3,6と足繁く通い続けている。何が面白いんだか・・・自分でも呆れる。
しかし一方,左岸(砂嘴先端)の地形変化を記録することは【花畔・網】としては当初からの最重要課題である。こちら関連の報告は5/27版をもって途絶えているが,先端の劇的な伸び縮みも見られず,ドラゴンも地上に安住していて変化に乏しいのでサボり続けていた。
今回急に思い立って Googleさんの過去画像を並べてみた。2019年,2022年については使える画像が見当たらなかったので,とりあえずは2017年から今年までの最近7年間の変化ということで見てみたい。
すぐに分かることは,2018年以前(Aとする)の画像と,2020年以降(Bとする)の画像とには明かな違いがあるということ。
Aでは,石狩灯台から砂嘴先端までの距離は約1500m。そして各年1枚の画像からでは到底分からないが,夏には先端が上に伸び,冬にはそれが圧し潰されてその分川幅を狭めるように右にせり出す,という季節的な変化が毎年のように繰り返されていた。
一方Bでは,灯台から先端まで約1300m。多少は伸び縮みするにせよAに比べると200mほど縮んだまま。顕著なのは背景画像中赤楕円で示した川岸部分の膨らみが上流方向(図では下方向)へ年々継続的に発達しつつあること。先端方向へは気まぐれに伸びることがあっても安定しない。
ではAとBとの間に何があったのか。2019年秋から2020年夏にかけて砂嘴先端が激しい浸食を受けて押し潰され,その分川側へと土砂が押し出された。それ以降この変化が定着,常態化してしまっているのだ。何故だろうか。上流から流されてくる土砂,沿岸を動く漂砂の増減,川の流れ,潮の流れ,さまざまな要因はあるのだろうが,差し当たり説明はつかない。
そこでついでながら,私が写した下4枚の画像。
私には毎回同じ位置,角度で眺望する定点観察点が数多ある。この4枚の画像の定点の設定は,注目に値する動きを察知した2021年後半のある時期からだ。だからそれ以前の画像はないのだが,堆砂の寄り付きが年々手前に迫ってきていることがよく分かる。この現象も右岸の堆砂の寄り付きに類似しているが,4年以上に及んで一貫した動きであることも侮れない。
ということでこの話,ここんとこ何度も三度も書こうと思いながらその都度,うたた寝したり,徘徊したり,八つ当たりしたり・・・
5日ぶり,ようやく更新することができた。書き損ないもあるかもしれないけど,めでたい。 |
| 2024.11.02版 |
|
秋の移ろい,の巻 |
|
紅葉山公園 |
|
12/1 追補 |

9/2 |

10/1 |

11/2 |

12/1 new |
|
エゾリスは,昨日も今日も現れてくれなかった。天気が悪かったせいかもしれないし,お爺さんが見逃したのかもしれない。もしかしたら,浜辺で拾ったクルミなので,しょっぱくて驚いたのかもしれない。
まぁいいや。いまこうして向き合っている作業用のパソコンは10年と8ヶ月のつきあいになる。すでにくどくど書いているようにしょっちゅうヒステリーを起こして動かなくなる。昨日は突如デバイスエラーと表示され勝手に再起動。PIN(暗証番号)を入力後”ようこそ”画面が延々4時間続き一切の作業を拒絶された。これはそろそろ寿命なのかもしれない。人生最後のパソコンに買い換えなければと思い,昨夜から今日の昼過ぎまで必要なファイルをハードディスクにコピーするバックアップ作業に追われた。ただ,いま新たにパソコンを買っても,それを使いこなせるようにセットアップできるかどうか,はなはだ自信がなくなっている。5年ほど前の自分はすでにいない。
うろうろと外に出る。幸い雨も上がってくれた。紅葉山公園の紅葉も終わりかけている。過去の画像を探すと,うまい具合に月一のペースでこんな気分になっていることが分かった。それもあながち悪くはない。
9月にはカメと出会って報告した。実は10月にもホースにしがみついていたのだが,さすがに朝晩冷え込む11月には姿がなかった。来年もまた会えるのかどうか。ああ見えて彼も必死に生きているのだろう。
【12/1 追補】 一ヶ月ぶりの紅葉山公園。樹々は葉をほとんど落とし,オンコとナナカマドの実の赤が際立っている。11/29に積もった雪もあずまやの脇に僅かに残るのみ。でもこの冬は大雪との予報。一ヶ月後は間違いなく銀世界。 |
| 2024.10.31b版 |
|
エゾリスに救われる,の巻 |
|
時雨虹を追っかけての一句 |

a |

b |

c |

d |

e |
|
たくさん撮った写真の中からこれはいけるぞと思うものを選び出して,いつも使っている何通りかのアプリケーションを用いて画像を加工整形し,それらの画像を組み合わせて表示する文章を構想し,閲覧用のブラウザ(EdgeだとかFirefoxだとか)に表示可能な形式の書体(html)に変換する。何通りかの手続きを踏むことになるのだけれど,大体は決まりきった手順を踏めばいいだけのことで,への河童だ。いや,だった。
近ごろその決まりきった手順を思い出せなくなることが時おり起きる。つまり,次にどうしたらいいのか分からなくなるのだ。もがくことになる。周りに八つ当たりすることにもなる。
道に迷うということは,もしかしたらこういうことなのかもしれない。いつものように目的地に向かって歩いているのに,途中の交差点でふと右に行くべきか左に行くべきかが分からなくなってしまう・・・ということに通ずる現象なのかもしれない。
お爺さんは,実は不安なのだと,声を大にして叫びたい。
そんなお爺さんは浜辺に行くといろんなものを拾って持ち帰る。たとえばクルミ。浜辺には驚くほどたくさんのクルミが転がっている。それからドングリ。石狩の浜近くにはカシワの木が自生し実をつけている。
それらの木の実を庭に転がしておく。花川にだって野生の生きものが結構いる。リス,ネズミ,モグラ,キツネ,ウサギ,タヌキ,シカ,クマ・・・ウソだ,クマにはさすがに出会ったことがない。
差しあたっていまの狙いはリス,エゾリスだ。さっそく今朝6時半過ぎ,現れてくれた。嬉しい。
クルミのほか,隣家のイヌバラの実(ローズヒップ)もお目当てらしい。
しばらくは彼らとの朝の出会いが楽しみである。時雨虹を追いかけても道に迷わずにすみそうだ。 |
| 2024.10.31a版 |
|
更新が思うに任せない,の巻 |

a |

b |

c-1 |

c-2 |
|
年甲斐もなくウロチョロしているので,更新のネタはそれなりにある。そればかりでなく,プーチンだ,ネタニエフだ,トランプだ,裏金だ,闇バイトだ,なんだかんだ・・・腹立つことも目白押しだ。けど,パソコンに向かう前にうたた寝してしまって,目が覚めても廃人同様にぼぉ~としてしまって筆が進まない(なんて,格好つける)。これは紛れもなく認知機能がじわじわ衰退しつつある証左に違いない。まぁ,抗ってみたところで来るものは来るのだから仕方がないのだけれど,今朝は庭にエゾリスが遊びに来てくれて嬉しかったので頑張って更新したい。
(a) 八幡の堤防を走っていると,時々キツネと目が合う。これは10/11。石狩川の右岸は右岸だけど,かなり離れているので第二突堤近くで出会って友だちになった(と,勝手に思っている)仔ギツネとは違うだろう。スマホに録音した声を聞かせてもキョトンとしていた。友だち仔ギツネに関しては,6/26版,6/21版,6/17版,6/7版に詳しい。彼の姿は,6/25に,テトラポットに隠れるシッポが見納めとなった。
(b) 10/15,これも八幡の堤防での目撃。この時期から年末にかけて現れるムクドリの群れに違いない。川岸のアキグミの実を啄ばみにくるようだ。その後も何度か見かけたが,まだ左岸では目撃していない。
(c) これは10/28。終日小ぶりの雨雲が次々に通り抜け降ったり止んだり。この時期特有の時雨(しぐれ)模様。合間に日が差すと北の空に時雨虹。住宅地で虹を撮る時は,よそ様の家の窓が入らぬよう気を遣う。ともあれ私にとっては今年初めての虹だったような気がして,出たり消えたりするのを追いかけまわした。
(番外) 10/30,石狩俳句コンテスト,今年の天位句『けあらしや鮫様棲むといふ大河』の木碑が立てられた。
(番外) 10/26に行われたらしいのは,石狩灯台のイベントなのか,灯台にぃちゃんのイベントなのか? 北海道新聞の提灯記事(10/31)。石狩灯台マニアを自称する私も,近ごろはこうしたイベントにうんざりしている。 |

a (10:57) |

b (11:37) |

c (11:43) |

d (11:51) |

e (12:24) |

f |
|
10/23版にも書きましたが,10/21は,10/18に続いてそれ以上に第一突堤が海面上に姿を現してくれました(a-e)。
確認した時間帯での石狩新港潮位は,18日でマイナス15cm程度,21日ではマイナス25cm程度と推測されますので,当然21日の方がめったない程の好条件です。
今回の背景は,(a)小樽高島岬。 (b)来札水制工とその手前に第三突堤。 (c)対岸・左岸砂嘴先端。 (d)北防波堤と洋上風車。 (e)離岸堤の端っこ。
とりわけ (c) に注目すると,第一突堤がふたつのゾーンに分かれていることが確認できます。向かって左側が浜側のゾーン,右が沖側のゾーンで,沖側のゾーンは海面上すれすれで波が下がらないと現れません。通常見られるのは浜側のゾーンです。
また直接関係ありませんが,(d) では北防波堤や洋上風車のジャケット基礎が空中に浮く下位蜃気楼も確認できます。
(f) もののついでですが,10/18には第二突堤先端のテトラポットまでたどり着くことができ,このテトラポット上から河口導流堤の激写に成功しました。10/4以来2度目のオッカナビックリでした。 |

10/20 (11:16) |

10/21a (11:27) |

10/21b (11:27) |

10/21c (11:42) |
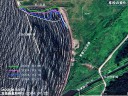
A |

B |
|
10/19版に書いた通り,10/20,10/21と2日続けて右岸。第二突堤詣で。
10/20は石狩湾潮位マイナス15cm程度。Good!ながら生憎の強い北西風。波も結構あって水際を歩くのもやや怖。
10/21は潮位マイナス20cm以下!南東風で波静か。まさしくお誂え向き。恥ずかしがり屋の第一突堤もバッチリ。
しかしその件はまたの機会に譲って今日は第二突堤に寄り付いている堆砂の動き。ますます大きくなりつつあって,同じ尺度の画像ではとても入り切らなくなってきた。10/20では手前側に肥大化し,10/21ではa,bに分割せざるを得ない。
ここまではこれまでと同様,定点観察点Ta点からの画像だが,今回はさらに150mほど南の崖の上のTb点からも眺めてみた。その画像が(10/21c)である。
堆砂の形をより実感可能なようにGoogle Earth画像に歩いたGPS軌跡を落とし込んでみたのが(A,B)である。
堆砂領域がかなり大きいことが分かるが,謎は,これらの堆砂の供給源はいったいどこにあるのだろうか,ということ。最近これに見合う浸食が近くにあったとも考えられないので,普通に考えると海中に漂う沿岸漂砂が潮流(向岸流)に乗って運ばれてきたとするのが妥当なのかもしれない。最近いよいよもの忘れがひどくなってきたお爺さんにとっては,難題である。一緒に考えてくれる若者はいないのか。
ま,それはともかく,次は11月半ばまで,極端に潮位が下がることは期待できない。 |
| 2024.10.19版 |
|
老いの執念,昨日の続き,の巻 |
|
今日は第二突堤 |

6/11 (12:26) |

10/11 (13:28) |

10/13 (11:08) |

10/15 (11:00) |

10/17 (9:20) |

10/18 (9:42) |
|
第二突堤への堆砂の寄り付きに今年初めて遭遇したのは9/23。(9/25版参照)
ここでは得意とする定点観察点(第二突堤付け根の崖の上のTa点)から眺めた画像を並べてみた。なにごともなかった6/11と,日々堆砂が動いている10/11以降の画像である。10/13は強い北西風で海は荒れていて,潮位も高かった。(これら以前の10/4の画像は10/8版参照)
9/28版で,堆砂が寄り付く前の9/1,9/12の画像を並べてあるが,6/11の画像とほとんど変わらない。すなわちこれが,第二突堤南側のごく当たり前のの情景で,6/11画像の中で赤矢印を施したテトラポットの先には普通は進めなかった。それが今のところ第二突堤先端近くまでラクラク進めるのだ。
しかも寄り付き堆砂は見て分かるように拡大しつつある。寒冷前線が通過した今日はなすすべもなかったが,明日は寒気を伴った強い高気圧に覆われるという。11時半ころが干潮。見逃せない。西高東低の気圧配置でかなり荒れ気味みたいだけれど,波に浚われないようにお爺さんは気をつけよう。 |
| 2024.10.18版 |
|
老いの執念,の巻 |
|
右岸・第一突堤にこだわる |

a (9:07) |

b (9:52) |

c (10:06) |

d (10:20) |

e |
|
昨日も書きましたが,ほぼ一日おき,そして今日(10/18)は昨日に続いての連日。向かった先は右岸第二突堤。というより,この間第二突堤がらみで書いていますが,本命は実は第一突堤。
昨年末の11/27,そして12/15に見たのが彼の最後の姿だった。通常の潮位では彼は生き残っていたとしても海面下で見られない。高気圧下の干潮時が絶対条件。今日やっと,午前9時から11時にかけて潮位マイナス10cm以下という願ってもない条件。老いの一徹のお爺さんは,文化祭もヘチマもあるもんかと頭を出した第一突堤を様々な角度から狙ったものでした(a-d)。
(a)の遠景は小樽高島岬。 (b)は来札水制工とその手前に第三突堤,さらに手前に2本ほどの第一突堤。 (c)は対岸・左岸砂嘴先端。 (d)は離岸堤の端っこ。いずれにしても彼は,海面下でも健気に生き続けていたことが確認されました。
ついでに近ごろクローズアップされてきた第二突堤に寄りつく堆砂(e)。いよいよ肥大化しつつあり,この先どこまで成長するのか目が離せません。ということは,これからも通うってことなのかしらん? |
| 2024.10.17版 |
|
明日から石狩市民文化祭・展示部門,の巻 |
|
Topicsは1週間のご無沙汰でした |
 |
|
今年の石狩市民文化祭・展示部門は18日(金)から20日(日)までの3日間。
石狩市花川南コミセンで開催されます。
石狩かしわ俳句会も参加しますので,今日午後,展示作業を終えてきました。
ご覧いただければ幸いです。関係ありませんけど,選挙も始まりましたし。
私は早くも期日前投票を済ませました。 |
前回10/10版以降,決して寝ころんでいたわけではありません。10/11,13,15,17(今日)と,一日おきに右岸第二突堤近辺に出没しておりました。堆砂の寄り付きが思いのほか成長し続けているのです。
でも,同時にその他の事柄,トウネンのこと,キツネのこと,ムクドリの群れのこと,木の実のこと,などなど,書こうと思うとメンドクサクなってしまうのです。今夜もこんなこと書き始めた途端眠たくなってしまいました。
スーパームーンも撮りましたけど,普通の満月でした。
明日は大潮。干潮+高気圧。またまた右岸に向かう予定です。文化祭どころではありません。 |
| 2024.10.10版 |
|
もっと第二突堤先端から河口導流堤,の巻 |
|
知津狩川左岸から |

a |

b |

c |

d |
|
一昨日(10/8)左岸砂嘴先端から第二突堤と河口導流堤を遠望した(昨日のe図)。そして昨日(10/9)は,右岸知津狩川の左岸堤防上から角度を変えて第二突堤と河口導流堤を遠望した。
(a) は2基の離岸堤と第二突堤,そしてその先に続く河口導流堤
(b) は第二突堤の基部方向。
(c) は第二突堤先っちょのクローズアップ。昨日の(b)との対比。
そして(d) が全体図。
A が10/8 左岸砂嘴先端からの視角。距離約750m
B が10/9 右岸知津狩川堤防からの視角。距離約450m。 |
| 2024.10.08版 |
|
第二突堤先端から河口導流堤を激写,の巻 |
|
9/28版とも見比べてください |

a |

b |

c |

d |

e (10/8) |
|
花畔大橋下をうろついた10/3以降連日,午前10時ころから正午過ぎにかけての観察最適時間帯に干潮を迎え,さらに高気圧に覆われて潮位がぐっと下がる日が続いた。じっとしていられない老人は,10/4,5,6と連続してでかけたのだった。訪れた時間帯での潮位は,いずれも0~マイナス5cmそこそこ(この値は東京湾平均海面を基準としての石狩湾海面の標高値である)。
タイトル通りに第二突堤先端から河口導流堤を望めたのは,実は10/4のみ。だから上の(e)を除く4枚の画像はいずれも10/4のものである。
(a) は9/28版同様,第二突堤付け根の崖の上のTa点から撮った光景。第二突堤に寄り付いた堆砂の領域が9/24よりさらに相当拡大していることが分かる。
(b) この日は突堤先端まで堆砂が続き,先っちょのテトラポットまで到達可能。
(c,d) ここからほぼ直角に折れて延びる河口導流堤を激写。こんな光景,誰も見たことないでしょっ!
次の日(10/5)もさらにその次の日(10/6)も再び見たくて行ったものの,先っちょまでの到達は不能。
水中を悠然と歩くアオサギに自分もなったかのように水中をうろつき始める同伴者も現れたりして焦る。これはいかんと,引き上げてきたのだった。ついでに,秋晴れの日曜日とあって,灯台の周りでモーターパラグライダーが遊んでいた。
そして今日(10/8),ヴィジターセンターを起点に左岸砂嘴をひと回り。疲れを知らない?。砂嘴先端から第二突堤の先っちょあたりを遠望した画像が(e)である。先っちょで,第二突堤から導流堤へとほぼ直角に折れ曲がっているのだが,これだけ離れるとほとんど真っ直ぐ繋がっているかのように見える。 |
| 2024.10.06版 |
|
うようよ,の巻 |
|
3度目のサケ・ウオッチング |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
今年初めて,ボクサナイ川へのサケの遡上を確認した9/16以降,石狩(厚田でも)まともな雨はほとんどない秋が続いた。川の水量が少なければ遡上が阻まれる。10/4,ようやく振り払うかのように降雨。ヒガンバナの開花を見届けた昨日(10/5),早速厚田まで走った。
恒例の,まずは厚田川河口の光景。好天ながら,釣り人はちらほら。
目指すは,支流ボクサナイ川・サケ二次飼育施設脇。厚田川河口では昨日の雨で濁っていた川水もここでは澄んでいて,しっかり堪能できた。しかしほんの少し上流の床止め近くでは昨年までとまわりの様相が異なり,河原に下りることも不能。サケたちはいるにはいるのだが,きちんと画像に捉えることはできなかった。 |
| 2024.10.05版 |
|
ヒガンバナが咲きました,の巻 |

9/26 |

9/28 |

10/2 |

10/4 |

10/5 6:11 |

10/5 14:42 |
|
ヒガンバナたちにとってはおそらく,開花するには過酷な寒冷地(というよりきっと,積雪地)である石狩の露地植えで,20年持ち堪えてくれました。今年は9/25に1ヶの花芽。その後待てど暮らせど現れず,今年の花茎はたった1本のみ。まぁいいか,咲いてくれたんだから。
2022年は9/20花芽発芽,9/30開花,花茎6本。
2023年は9/17花芽発芽,9/26開花,花茎24本。【過去最高】
2024年は9/25花芽発芽,10/5開花,花茎なんとたったこれ1本。【近年では最低】
とんでもないはなしです。
画像追加 : そして開花2日目の10/6。6:02,16:34。 |

a |

b |

c |

d |
|
|
10時ころが干潮,しかも103(ヘクトパスカル)近い高気圧下。気圧に押し下げられて日中の潮位は相当下がるに違いない。ならば,右岸だ。
と思いながらもグズグズしていてメンドクサクなった老人は,お昼前後,茨戸川左岸の花畔大橋下をウロつくことになってしまった。自分でも思いがけない展開ではある。ずっと奥歯の痛みに苦しんでいたこととは関係あるのかもしれない。
つまるところ本当に久々,岡﨑文吉が遺した単床ブロック遺構に会ってみたくなったのだ。これだけ潮位が下がれば,遺構のブロックも頑張って顔を出しているに違いない。
いまにして思えば,2019年ころまでは単床ブロックに凝っていた。翌2020年3月コロナ初期,志村けんさんが亡くなった。翌3/30に界隈を歩いた。実はその後ほとんど歩いていない。
石狩治水遺産研究会なる組織?が,岡﨑の足跡を洗い出し始めたこととはまったく関係はない。私自身がもう十分調べたと思ったからだ。
そしてその研究会なる組織はいまはない,という。なんなんだ。岡﨑も浮かばれないのではないのか。まぁいい。好きにしなさい。私の頭の隅からは,単床ブロックは離れない。 |
| 2024.10.01版 |
|
出雲さんから保護センターへと抜ける道,の巻 |

a |

b |

c |

d |

e |
|
|
9/27未明に激しい雷雨があったが,それ以降今日までずっと好天。おかげで,一昨日(9/29)訪れた第59回石狩さけまつりもたいへんな賑わいだった(a)。でもでも,人混み苦手な老人(なら,初めから行かねばいいのだ)は逃げ場を求める。
まつりの会場となっている弁天歴史通りの一角に曹源寺がありそれにほぼ隣接して出雲教大神社(出雲さん)がある(b)。歴史通りからやや奥まっているのであまり気づかれない。この社のすぐ脇から,小高い砂丘(といっても草木に覆われている)を越えて浜へと続く踏み分け道がある。いや,あった。今年も5/18に歩いて,道なき道化した獣道になっていることを知っていた。けれど人混みから逃れてほっとするのには格好のスポットではないか・・・
こ,これわっ!踏み分け道,どころか,完全な藪(c),である。ヤマブドウの太いつるなどが横に伸びて通せんぼ。道などない(d)。戻るにも戻られず,老人は無我夢中で標高10mほどの天辺にたどり着くことができた(e)。
ここは『展望の丘』(私は勝手に,”弁天の丘”と呼ぶ)。保護センター側からは登る道がしっかりと整備されている。
この小径は過去に何度か歩いたことがある。それがこれほど鬱蒼とした藪になっているなんて,驚くなかれっ!だ。
往時の面影のない道,過去にさかのぼって,若干の蘊蓄が必要な気がする。 |
2013.09.29

f |

g |

h |

i |
|
|
膨大な画像収納庫をひっくり返して探した。そしてこれが,私にとってのこの小径の最初ではないかと思われる画像たちだ。
奇しくも11年前のさけまつりの日だったようだ。
(f)がこの日の出雲さん。社は1996(平成8)年に建て直されたということだからまだ20年も経っていない頃だ。
その脇に,車両の通行は禁止されているが,綺麗に刈り込まれた小径が浜に向かっている(g)。砂丘の道も整備されている(h)。
天辺に上がるとそこには『弁天の丘』の標識(i)。その後なぜか『展望の丘』などというつまらない名に付け替えられたのが癪で,私は”弁天の丘”と呼び続けている。
(i)の画像の右下に小さな標識が立てられていて,そこに「弁天歴史公園の近道」と記されている。つまり,出雲さんからの小径は海浜植物保護センターお墨付きの近道だったのだ。ところが今年の丘の天辺には,ほとんど同じ位置に「市有地につき立入禁止」の看板が・・・なんてこったい。
1937年竣工して一度も営業されずに,1945年米軍の空襲により焼失した石狩海浜ホテル。ホテルへと本町側から通じていたのもこの道だったに違いない。 |
このページについてお気づきのことがありましたらお知らせください
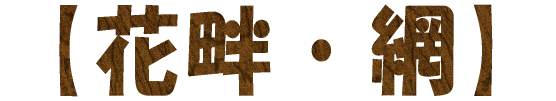









































_241013_thumb.jpg)
_241126_thumb.jpg)