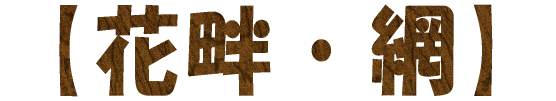2025.09.30b版 駆け引きはつづく,の巻 犯人はいったい・・・?
A1 - 9/28 16:46
A2 - 9/29 5:52
B1 - 9/29 7:52
B2 - 9/29 20:25
C1 - 9/29 20:25
C2 - 9/30 5:46庭にクルミを転がしておくといつの間にかなくなる。何故か必ずなくなる。しかし,犯人を目撃できない。
リスだろうか,ネズミだろうか,カラスだろうか,キツネかな,ヒトかな?????
ただしいくつかのクルミは絶対になくならない。半分に割れて中身がなくなったクルミ(6ヶ)と,昨年浜で拾ってきて転がしておいたのだけれどリスたちがついに見向きもしなかったいかにも美味しくなさそうなクルミ(3ヶ)だ。
ヒガンバナ開花の項で多忙と書いたにもかかわらず,お爺さんとしては犯人を突き止めたい。犯人が無視している9ヶに,1ヶだけまともなクルミ(画像中の〇印)を混入して放置してみることにした。
A 9/28夕方セット(1) 9/29早朝なくなっていた(2)
B 9/29朝セット(1) 夜暗くなってから覗くとなくなっていた(2)
C 9/29夜,コンチクショウと思いすぐにまたセット(1) 今朝早くセットした1ヶだけ姿を消していた(2)
当然ながらすぐにまた1ヶセットした。これを書きながらしょっちゅう窓の外に目をやっている。15時30分現在まだなくなっていない。
犯人像を激写することはできるだろうか?
[追記] そして,やっぱりやられてしまった。今夜はほぼ上弦の月。18時ころからずっと懐中電灯を点けたり消したりしながら監視し続けたお爺さん。根気が足りないことをつくづく思い知らされることになる。19時半ころさすがにあきる。歯を磨いてそろそろ寝るべ。そして20時,寝ようと思って最後の確認。なくなっていた。脱帽!!!!!
[追記2] 負けてはいられないお爺さんは,10/30,20時過ぎすぐさまクルミを補充。翌10/1早朝,やっぱりなくなっていた。
2025.09.30a版 ヒガンバナの開花,の巻 3枚とも本日早朝の撮影です
c,d
a,b
eご無沙汰しました。なんの予告もなしに突然ポックリいって【花畔・網】終焉か!!!と,誤解された方もいらっしゃったかもしれませんね。だとしたら,残念でした…ではなくて,申し訳ありませんでした。
9/20にアオバトとサケの遡上を求めて厚田まで行ってきました。押琴浜でも,ボクサナイ川でもペケでした。その夜からいきなり私事多忙。一週間あまり更新する余裕もヘチマもありませんでした。昨日(9/29)やっとどうにか石狩川河口右岸を歩き,この秋流れてきたクルミ(エゾリスおびき寄せ用)を沢山と,今年初めての琥珀をたった1ヶ拾ってきました。狙いはここんとこ毎年繰り返される秋の堆砂でした。狙い通りでしたが,それはまたのちほど。
しばらくぶりの今日は,9/19版の花芽に続いてたちまちヒガンバナのお花見です。結局花茎は(a)から(g)まで7本顔を出してくれました。うち今朝までに開花したのは(a)から(e)までの5本。
9/19版で(b)は赤と書きましたが,白の間違いでした。(a)の最初の一花が開いたのは9/27でした。
(c,d)はひとつの株(球根)から揃って伸びてきた花茎で,9/19版の(c)の画像をよく見るとちっちゃい花芽が頭を覗かせていることが分かります。それが(d)です。先に咲いたのは(c)で(a)と同じ9/27でした。
(e)は庭で20年持ち込んだ株。9/20に花芽が現われ,9/28に一番花。
(e)以外の6本はすべて我が家では7年目の株です。
なお,(c,d,f,g)は,我が家の塀の外,市道の芝の張り込みの中で育っていますので,市道を通行中でも気軽にご覧いただけます。
2025.09.19版 ヒガンバナの花芽,の巻
a
b
c9月といえば,初めは夏で,終わりは一気に冬だなぁ・・・などとしみじみぼんやりしていたら,ヒガンバナの花芽が顔を出していた。
去年見つけたのは9/25だったからやや油断していた。
(b,c)は2cmほどだから今朝顔を出したのかも知れないが,(a)は4cmほどもあり,きっと昨日か一昨日出たに違いない。
花色も,(b,c)は赤で,(a)は白。楽しみ。
2025.09.16版 今年も石狩川の橋の旅,の巻
A - 1
A - 2
B - 1
B - 2
C - 1
C - 2
D - 1
E - 1
D - 2
E - 2
E - 3
F - 1
F - 2
G - 1
G - 2
G - 3
G - 49/13から9/15まで個人的な所用があって遠軽・湧別・留辺蘂方面に出かけてきました。おそらく車で行く(運転して)のはこれが最後かと思われます。
さりながら,石狩川に沿って走っている分には,架かる橋との付き合いを忘れるわけにはいきません。
実は昨年も9月初めに行ってきて,ご報告させていただきました。
ので,今年もいかせていただきます。
(A) 妹背牛橋。新橋はとっくに出来上がっているが,旧橋の撤去作業の進捗状況が面白い。(-1)は昨年9/9。(-2)は今年9/13。旧橋の異彩を放っていたトラスがついに消滅していたのがなにかしら悲しい。
(B) 比布大橋。架替が新規事業化してもはや10年。遅々として進まない新橋工事。(-1)は昨年9/9。(-2)は今年9/13。ほとんど変わらない。
(C) 七戸の吊橋。吊橋が崩落して9年。よほどの物好きでないと訪れる人もいないかもしれない,しかしわたし(たち)には,道の駅かコンビニで買った弁当をここの河原でゆったりと食するのが至福のひと時。(-1)は昨年9/9。実に至福。しかし(-2)は今年9/15。前日来の大雨で増水。河原で弁当,どころの騒ぎではなかった。
(D) 菊水10線の吊橋。今年は寄らなかったので(-1)は昨年9/9。今年は200mほど上流に新設された菊水新橋から望む(-2)。
(E) 菊水新橋。石狩川に架かる橋で最も新しい橋。(-1)は昨年9/9,下流の菊水10線の吊橋から望む。(-2)同じく昨年9/9,工事中で近づくことは不能。昨年暮れに開通。(-3)は今年9/13。真新しい。
(F) ホテル層雲・本館別館渡り廊下。<実は下の彩雲橋より上流> (-1)は昨年9/9。渡り廊下の撤去作業中。そして(-2)は今年9/13。跡形もない。
(G) 彩雲橋。国道39号と廃業したホテル層雲本館とを結ぶ町道に架かる橋。(-1)昨年9/9にはホテル層雲はしっかりその姿を留めていたが,(-2)今年9/13にはホテルはもはやない。一度は泊まったことがあるだけに,なにかしら寂しい。(-3)橋を渡っているのはシカ4頭。(-4)そして翌々日の9/15,再度通りがかると工事のために補強されたと思われる高欄の下流側が撤去されてなくなっていた。もしかしたら彩雲橋そのものもまるごと撤去されてなくなってしまうのかもしれない。
2025.09.12b版 続・旅鳥の季節,の巻 前編は9/5
m
n
o
p
q
rすべて9/9の石狩浜。
(m,n) 草原で群れるツバメたちと思われます。だからこの近辺で子育てを終えた,厳密には旅鳥ではなくて夏鳥に括られます。
(o-r) 大型の鴫,オオソリハシシギの6人のファミリー。
2025.09.12a版 脈絡なく,の巻
(a) 9/6
(b) 9/6
(c) 9/9
(d) 9/9(a) トノサマガエル。右岸,旧聚富川河跡の水たまり。水面をよく見ると結構たくさんいることがわかる。2023年にも何度か見かけた(8/20版,9/9版)
(b) サケ定置網。8/31にも沖合1.5kmあたりに運動場や箱網などが設置されていたが,9/6にはほぼ直角に張られる垣網が浜に固定されていた。垣網で進路を遮られたサケたちは,網沿いに進んで運動場に誘いこまれる。
(c) 保育園児たちと灯台。それだけ。
(d) ハマナスの花はあまり撮りたくないへそ曲がりなお爺さんも,ついシャッターを切ってしまった。。
2025.09.08版 皆既月食,の巻 部分食から皆既食まで
1:15
1:27
1:42
1:59
2:16
2:29酔狂なお爺さんとお婆さんは,午前零時に目覚ましをかけて皆既月食を堪能?してきました。行った先は2基のガントリークレーンが並ぶ花畔埠頭です。対岸・樽川埠頭の上空を西の空に動いていきました。場所が場所だけに夜釣りの人もいましたが,三脚つけたでっかいカメラを担いでくる人も結構いました。
皆既食に入ってからは私のカメラと腕とでは赤いお月さんに太刀打ちできず,おまけに寒くなって早々に引き上げてきました。
今朝確認すると,カメラの時刻が4分48秒ほども進んでいた(きちんと手入れしていないこと歴然)ことが分かり,上の時刻は補正してあります。
2025.09.07版 芋虫毛虫,の巻
a
b
c
d【花畔・網】ではしばしばチョウやガの幼虫の芋虫/毛虫を取り上げます。2大代表選手は,キアゲハの幼虫とチャドクガの幼虫です。
例えばキアゲハでは,8/15版,6/27版,6/20版,など。ドクガでは,7/16版(成虫),6/13版,5/29版,など。(ただし今年に限る)
キアゲハの幼虫は体に毛のない芋虫系,チャドクガの幼虫は体が毛やトゲに覆われた毛虫系の代表選手です。
そのほかではシャツにくっついてきたシャクトリムシが1度登場(6/4版)しましたが,これも芋虫系ですね。
とはいえ,正直なところお爺さんはこの手の虫は苦手です。ドクガはもとより,毒のない芋虫たちも手で触れるのはご遠慮。できることなら目に入れたくもありません。
にもかかわらず一昨日(9/5)のこと,海浜植物コーナーのエゾカワラマツバにびっしりと緑色の芋虫たちがくっついているではありませんかっ!(a)その数ざっと30匹。大きいものでは太さ10mm以上,長さ6~70mm(b,c)。お尻の背中側に角のような突起(尾角)を備えているところからして,どうやらスズメガの幼虫に違いありません。しかしスズメガにも様々な種類があり,同じ種類の幼虫でも黄色くなったり黒くなったりで,結局種類を突き止めるのは翌日以降,としました。
翌朝(9/6),ご挨拶に伺うと,そこにはただの1匹もいませんでした。大量のウンコの置き土産(d)のみ残して…もっとも集っていたエゾカワラマツバの葉は食べ尽くされた状態ですから,いても仕方がないのかもしれませんが。突然いなくなる原因としては,鳥などの捕食者に食べられてしまったか,周囲の土に潜り込みそこで蛹になったかが考えられるとGoogleさんはいうのですが。
今日(9/7)ほじくり返してみてもみてもそれらしいものは見つかりませんでした。カラスにやられたのでしょうか。
それはそうと,まったく関係ありませんが,今朝(9/7)の北海道新聞日曜版・新五感紀行は縄文海進がらみで興味深いものがあります。
実は,俳句のまち~いしかり の今年の俳句コンテストに,
『語り継ぐ縄文海進波の花』
という句を出しました。やはり屁にも引っ掛けられなかったようです。"字引をひくまでもなく"の選者ですからねえ。
我ながらお粗末な俳句だし。
さりながら,さまざまな要因はあるにせよ(あるからこそ),地球の温暖化を考えるとき見過ごせません。
道新日曜版をぜひ読みたいという方は私にメールしてください。
2025.09.06版 モエレ沼花火,の巻
エアコンのない我が家は,夜も窓を開けっ放しだ。午後8時ころなにやら外が騒がしい。
2階の窓から覗くと,東南東に打ち上げられている。地図を開くとモエレ沼の方角。だとするとおよそ10キロ先。
「北海道芸術花火2025」というものらしい。すぐにカメラを構えるお爺さん。
送電線や鉄塔が邪魔だけど,まぁいいや。
2025.09.05版 旅鳥の季節,の巻
2025.09.03版 収穫の秋,の巻
亜麻-a
亜麻-b
ミニ田んぼ"収穫の秋"というほどのものではまるでございませんが,8/21になんとかメヒシバを始末した亜麻畑,すべて引っこ抜いてタネを収穫しました。メヒシバとの壮絶な戦いがあったせいか,今年は実入りがはなはだよろしくありません。でも来春撒くタネは確保できたみたい。
収穫話のついでに,昨日9/2のミニ田んぼ。8/14に比べるとすっかり黄金色。今度行ったら刈り取られているのかも。
2025.09.02版 押琴浜ハマボウフウ大作戦,の巻 4年目
a - 9/1
b - 9/2
c
d1
d2押琴浜にもハマボウフウを!と,2022年秋から始めたハマボウフウ大作戦。樽川9線浜でハマボウフウの種を採集して押琴浜に蒔きつけるというもの。如何せんお爺さんもよれよれだし,結果にかかわらず昨年の3回目で終えるつもりだった。けれど押琴浜にもそれなりにハマボウフウが果敢に根付きつつある現状を見るにつけ,お爺さんにもここでくたばってはいられないという思いもつのり始めた。
というわけで,4回目を敢行。
(a) 昨日9/1,樽川9線浜にて種を採集。結構草臥れて例年より量は少ない。
(b) 今日9/2,朝10時ころ花川界隈はまだ小雨。えいままよ,とばかり出かける。ラッキーにも石狩川を渡ると雨はやむ。昨年播種,今年発芽の1年株のまわり,のみならず,持って行った種を1ヶ残らず撒き散らしてきた。
ついでに,昨日今日の出会い。
(c) 昨日樽川浜への入口に駐車すると,お婆さんが「なにかいるっ!」と叫ぶ。確かに草むらの中に蠢くアヤシイ,否,カワイイ影。ヒガシニホントカゲだ。はまなすの丘の木道の上では何度か遭遇したことがあるが,2020年を最期にお目にかかっていない。実に久しぶりの再会だった。きっといいことがあるに違いない。
(d) そして今日の秘かな期待は,押琴浜では今年6/28以来のアオバトとの遭遇。かなり離れた位置からの遠望でアオバトたちが群れているのを確認。ズームを手一杯効かせて撮ったのがこれらの画像。近づいたらすでに飛び去った後の祭り。それからはまったく姿を見せてくれなかった。お爺さんが我慢できるのは1時間そこそこだけれどね。
2025.08.31版 大時化とべた凪,の巻
a
b - 8/27
b - 8/31
c - 8/27
c - 8/318/27,浜(左岸砂嘴)歩き。9時ころまでは穏やかだったのに,歩き始めた11時ころには西風ガンガン強まる。先端に着くころには強烈。砂は飛ぶ,波しぶきは飛ぶ。悔しいけれど命からがら逃げ帰る。なんとか助かった。
そして今日8/31。川面も海面もさながら鏡のよう。気温も27℃止まり。快適。リベンジ成功!
(a) はナウファスによる石狩湾新港有義波実況。8/27は9時ころから有義波高がイキナリ高まり始めていることが分かる。13時ころにはヴィジターセンターまで退却完了して無事だったが,その後有義波高は4m近くまで達したようだ。石狩では年に1,2度5mを越す大荒れがあるかないかというレベル(一昨年10/6以来ない)なので,かなりの頑張りである。それに比べて今日8/31は未明から超・べた凪。こんな日もあまりない。
(b) 8/16版につづく非定点遠望。先端の最出っ張り点から対岸(右岸)の知津狩新橋を望む。8/11時点よりやや膨らんだ(出っ張った)ようだが,8/27と8/31とではほとんど変わらない。水面の状況はかなり異なるが。
(c) そして,8/27には巨大流木の手前にあったトドの亡骸。なんと8/31にはなくなっていた。状況からして波浪に持ち去られたとは考えにくい。おそらく,風と波の運ぶ大量の砂によって覆いつくされたのに違いない。
ちなみに,ご馳走はきっとこの辺り,とばかりにキツネやカラスたちが掘ったのであろう穴が数か所に見られた。
2025.08.25版 今日はクラゲです,の巻 海水温上がり宇宙に去る海月
2025.08.24版 やっぱりネズミだっ!,の巻
a
b我が家の庭です。一角にブロックや平板を敷いている箇所があります。そうです,秋から春にかけてエゾリスが遊びに来てくれたりします。その後エゾリスはほとんど姿を見せません。なのに転がしておいたクルミがいつの間にか数を減らしていくのです。初めのころはカラスのせいだとばかり思っていました。ところが1,2ヶ月前から,ときおり眼の隅に動く物陰を感じることがあるのです。そして今朝,正体をはっきりと捉えることができました。
Googleレンズに問い合わせると,「ハタネズミ」だといいます。しかしハタネズミは北海道には生息していないという話。だとすると,「エゾヤチネズミ」に違いないと思います。敷いてあるブロックの穴を絶好の隠れ家にしているのでしょう。体長10cmあるかなしかのちっこいネズミです。めんこい。日本での最小のネズミはトウキョウトガリネズミということらしいですが,石狩近辺の海岸近くではごくたまにその亡骸を見ることがあります(これが本当なのかどうかは自信ありません)。
2025.08.21版 雑草さん,ごめんなさい,の巻
Before 8/19
After 8/21亜麻畑のBefore-Afterです。一ヶ月前はこんなでした。ほんのひと月で悲惨な雑草畑に転じていました。
メヒシバ(雌日芝)というイネ科の草です。昨年までもチラホラ見受けられましたがほっといても大丈夫でしたが,今年は異常でした。
ほっといたお爺さんが悪いので,今朝(8/21),腰を据えてお昼までかかってなんとか始末しました。
それにしても今年のメヒシバには恐れ入りました。通常の草丈は30cmそこそこらしいのですが,亜麻畑では亜麻の草丈と激しく競いそれを凌駕しようとするようです。
我が家の草取りは,敷地内についてはお婆さんが舐めたように奇麗にやってくれます。お爺さんの担当は塀の外。つまり石狩市の道路用地の一部ですが,勝手に亜麻畑にしたり海浜植物コーナーにしたりしているものですから,仕方ありません。
お爺さんがヤだなぁと思う雑草,ベスト?ちゃう,ワーストファイブは
メヒシバ
カタバミ
スベリヒユ
コニシキソウ(orハイニシキソウ)
ヒメムカシヨモギ
といったところです。かつてスギナは目の敵にして退治しました。
2025.08.19版 あれこれ・その2,の巻 8/14
a
b-1
b-2
b-3
b-4これらは,アオバトが空振りに終わった8/14の行き帰り。厚田方面へ走るとき,石狩川の右岸から望来までの間はほとんど国道231を走らずに八幡・聚富・知津狩から望来間の海沿いの市道を走ります(ついでに,望来-嶺泊間も海沿いの段丘上を走ります)。
(a) 8/2版に続いて,旧知津狩川右岸添いのミニ田んぼ。いよいよ稲穂が出揃ってきました。
(b) この道を走っていていつも怪しんでいた光景があります。無煙から望来へ向かう段丘の上り坂の途中に車が何台も駐車していることがあるのです。狭い道路なのにアブナイなぁと思っていました。なんのことはない,お爺さんには無縁なパラグライダーの離着陸基地があったのですね。
この日は押琴からの帰路,車が1台も駐車していなかったので,自分の車を停めて海側の崖の上に上がってみました。
基地がありました(b-1)。誰一人いません。ついでに,こんなのとかあんなの。
少し離れて小さな赤い祠がありました(b-2)。この道路は冬季除雪されず望来側で行き止まりになりますが,この冬,そこから眺めると赤い小屋が見えて,不思議でした。この祠だったのですね。謎がひとつ解けました。
そして基地の崖っぷちからの光景です。崖の真下に見えるのが,今では見捨てられた無煙浜の船溜まりの突堤(b-3)と,石狩川河口導流堤からこちら側に伸びる知津狩,無煙の浜辺(b-4)です。
無煙浜といえばムカシは海水浴場がいくつかあって賑わっていたらしいのですが,かつては石狩音痴だったお爺さんはまったく知りませんでした。ほっつき歩くようになったのは【花畔・網】を始めた2007年から。最初に無煙浜にたどり着いたのは2009年の9月。料金所や売店が建っていました(シーズンオフのためか閉じていました)。パラグライダーといえば2010年の5月に崖の上に浮かんでいるのを目撃しましたが,ここにこんな基地があるなんて知りませんでした。まだまだ知らないことだらけで死んでしまうことになるのでしょうか。そんなこと知りません。
2025.08.17版 あれこれ,の巻
a
b
c
dお盆が過ぎて,雨。気温もせいぜい24℃ほど。少しだけ凌ぎやすい午後です。溜まった写真の中から4枚。
(a) 8/11,浜歩きした日,管理道路脇のメドハギがいくつか花を開いていました。なにしろ小さな花で,奥ゆかしいです。
(b) 浜辺では,2羽のミユビシギ。非定点遠望の他ではそんなくらい。
(c) 8/13,八幡の堤防を走っていると,目の前を横切って看板にとまった鳥。慌てて車を止めて撮ったけどややピンボケ。もしかしたらアカモズの幼鳥ではないかと思われます。
(d) そして昨日(8/16)のこと。6/15版のBefore-Afterの続編です。その後伸びたヒノキを2度目の刈りこみ。チョンマゲがだいぶ大きくなりました。
2025.08.16版 非定点遠望,の巻 左岸砂嘴先端の挙動⑥
2025.08.15版 ヒヨドリのファミリー?,の巻 8/12
f1
f2
f3
f4
g1
g2また,鳥です。敢えてお断りしておきますが,私は鳥を狙ってカメラで遊んでいるわけではありません。
といいつつ,アオバトとショウドウツバメだけは,その姿を捉えることを目的として出かけます。
実は昨日(8/14)もアオバトに会いに押琴浜へ。7/22とは正反対のべた凪。にもかかわらず空振りに終わりました。それでもハマボウフウたちは元気。食欲旺盛なキアゲハの幼虫にも会えました。
それはそうと,今日の画像です。今日の画像といっても8/12の画像です(f1-4)。なんとなく面倒臭くなりがちな今日この頃。暑さのせいにしてしまいましょう。
この日は朝,お坊さんが盆参りのお経をあげにきてくれたり,厚田から札幌に転居されたばかりのTさんが立ち寄ってくれたり,やれやれ今年のお盆も早くも終わったかな・・・と,ぼんやり外を眺めていた昼下がり,突如5,6羽のヒヨドリの集団が目の前の電線に留まりました。
1羽(親?)が大きな餌(虫?)を咥えていて,隣りの1羽(仔?)に与えようとしているように見えます。コムクドリもそうでしたが,巣立った後もしばらくはこうしてファミリーで支えあって暮らすのでしょうね。
【追加】そして本当に今日(8/15),風呂上がりに外で夕涼みしていたら,またまたやってきてくれました。お隣りさんちの屋根の上です(g1-2)。
2025.08.07版 ドバトの夫婦?,の巻
2025.08.06版 右岸アプローチが激変,の巻
7/28-a
7/28-b
8/4-a
8/4-b
測量-a
測量-b8/5版の白花ヒルガオに出会った7/28には,その前に石狩川河口右岸をうろついていました。アオバトには出会えませんでしたが,5,6羽のツバメたちが群れ飛ぶ姿を確認しました。ひたすら飛び続ける(しかも猛スピードで)ツバメたちの姿を私のカメラで捉えられる筈がありません。(´Д⊂グスン
そして一昨日(8/4),一週間ぶりに再度右岸へ。知津狩新橋脇の知津狩川右岸から石狩川河口右岸(海辺)へのアプローチが激変。
(-a) は石狩川河口右岸方向への全景
(-b) はその途中からほぼ90度北へ目を転じて,北石狩衛生センター方向を望んだ画像,です。
広く植生が刈りはらわれて,砕石が敷き詰められた工事用の道路が敷設され,しかもすでに重機が動き回っています。
聞くところによると,工事は8/2から始められ,残土の置き場になるのだ,という。すでにダンプがしきりに運んできていました。
ホーストレッキングや,我々ほっつき歩き族の踏み分け道は確保されていました。
海辺へ出ると,石狩川に合流する知津狩川河口あたりに数人の人影。どうやらラジコンボートで測量中とのこと。(-a)の後方に見える橋が知津狩新橋。
2025.08.05版 白花ヒルガオと五の沢ダム,の巻 7/28,29
白花ヒルガオ
五の沢ダム-b1
五の沢ダム-b2
五の沢ダム-c1
五の沢ダム-c2白花ヒルガオは7/28。
左岸本町,市道灯台線のマウニの丘脇に並べられた土のう。それを覆うように繁茂した植生に白い花が咲いている。このあたりでは見慣れない花。一見砂丘草原ではお馴染みのハマヒルガオのようでもあるのだが,近寄ってみると道端ではよく見かけるヒルガオの白花だった。とくに珍しくもない。護岸された川沿いでは以前からよく見かけた。
花の形はハマヒルガオもヒルガオもほとんど変わらないのだが,葉の形は,ハマヒルガオが丸く心臓形なのに対し,ヒルガオは長く矢じり状で先が尖っているのですぐ分かる。
でも,なんでこんなところにヒルガオが?土のうの中に紛れ込んできたか,工事の時に持ち込まれてきたか?
ハマヒルガオにも白花があるらしい。結構探してみたりするのだが,まだお目にかかったことはない。
五の沢ダムは,4/23版以来。(b) が 5/15,(c) が 7/29。
(-1) ダム奥(上流方向)を望む全景。5/15と7/29とでは,ダムの水位の違いが若干分かる程度。
(-2) 逆方向の洪水吐(こうずいばき)を望む。洪水吐は,ダムが満杯になった時,溢れた水を安全に下流に流す放流設備。
5/15では田植え前で農業用水は取水されておらず溢れて洪水吐から流れ落ちているが,7/29では取水されてかなり水位が下がったためすっかり緑。
このダムには取水孔が18ヶ設けられている。5/15には一番上の1番孔も閉じていたが,7/29には9番孔まで開いていた。
2025.08.03版 はまなすの丘ひとめぐり,の巻 7/23
a
b
c
d
e
f7/23ははまなすの丘ひとめぐり。前日7/22は石狩の最高気温32.7℃。続くこの日7/23は32.8℃。暑いうえにお腹の具合イマイチで,あずまや脇の簡易トイレに駆け込む始末。情けない。
それでも木道を先に歩き始めた幼児たちの姿にハゲまされてなんとか砂嘴ひと回りをまっとうできた。
まずこの日の花たち。
(a) 木道から見るオニユリの群落。石狩川を挟んでの遠景,手前左側は石狩霊園,奥右側に当別の阿蘇岩山。
あずまやから先の湿地帯では,タチギボウシはくたびれ気味。替わりに
(b) クサレダマ
(c) エゾミソハギ
それから・・・
(d) 巨大流木とその手前にトドの遺骸。4/2の画像とは異なり,まわりはすっかり緑地帯。といってもほとんどは一年草のオニハマダイコン。
(e) 浜辺で出会ったひとりぼっちのキアシシギ。
(f) なぜかトノサマバッタ。木道上で沈思黙考。
関係ないですが,今日はここの町内会の夏まつり。暗くなってからそそくさと写真だけ撮ってきました。
2025.08.02版 久しぶりの当別,の巻 7/22
a
b
c
d-1
d-2
d-3更新する気力の萎えた7/20ころからも,暑い中チョロチョロ出かけていました。我が家でエアコンが効くのは唯一車の中だけ。そんな事情もあったりします。
というわけでまずは,アオバト狙いの7/22。
(a) 6/21版に続く,途中のミニ田んぼ。緑がかなり濃くなっていました。
(b) 肝心の押琴浜は珍しく波高く荒れ気味。波に飲まれる危険を察知してか,アオバトたちは現われてくれませんでした。替わりに,6/30版以来の元気なハマボウフウ。
(c) 仕方がないので厚田から当別へ向かう途中,やまなみ滝。なんと昨年の4/7版,5/4版以来です。今年は初めて。この時期になると周りの樹木の陰になって存在感がイマイチです。
(d) そして昨年3/20以来の当別ダム。
(-1) 展望駐車場からの望郷橋。ちなみに,16年前,2009.11.24,工事中の望郷橋です。下の道路が当時の道道28号当別浜益港線。この道道沿いにあった集落はダム底に沈んでいます。しかし歴史は湖底に沈みません。沈ませてはいけません。オレンジ色が幅を利かせようとも。
(-2) 愛称が”亜麻のふるさと当別ダム”といわれるだけに,観賞用亜麻(多年草)の鉢植えが数鉢置かれていました。花はとっくに終わっていましたが。なお,亜麻仁油(種子から採ったオイル),リネン(茎の繊維を紡いだ布)は一年草の亜麻から得られます。
(-3) ダム下流広場から見上げた堤体。ここには”望郷の碑”も置かれていました。気持ちは分からなくもないけど,なんだかなぁ。
2025.08.01版 津波にこだわる,の巻
2025.07.31版 終わりました,いえ終わりません,の巻 カムチャッカ半島沖地震による津波
2025.07.20版 終わりました,の巻 7/12版の続き
7/13
7/14
7/15
7/17
7/18
7/207/5に5輪開花した我が家の亜麻です。およそ2週間で草臥れてしまいました。とりわけ18,19日の雨に打たれて今朝はやや悲惨。
来年も植えるかどうか・・・分かりません。
2025.07.17版 蜃気楼その5,の巻
D - (15:05)
C - (15:28)
A - (15:44)
A - (6/5)昨日(7/16)はお昼を挟んで石狩でも土砂降りの雨。雨雲レーダーによると,降水強度は1時間雨量50mmを越すほど。しかしさっさと通り過ぎて行ったので生振・アメダスの公式雨量は14mm。しかし石狩市内でもところによっては20~30mm降っていても不思議ではない。
石狩海水浴場あそびーちは7/12海開き。ようやく海水温も上がってきていたであろうに,万遍なくこれだけの冷水を浴びせられ海水表面温度が下がったのに違いない。そこにもってきて雨上がり後陸地の気温が急激に上昇。15時過ぎには29℃。その暖気が南東風で海上へ。というわけで,久しぶりに蜃気楼条件が整ったものと思われます。
お爺さんは暑さにメゲず右岸にコムクドリに会いに行ったものの肩透かし。
D - しかし知津狩新橋から小樽・高島岬を遠望して蜃気楼を確認。右岸側からこれだけ明瞭な蜃気楼を確認できたのはもしかしたら初めて,だったかもしれない。
C - 取って返して左岸へ。はまなすの丘公園の木道からも確認。ここからのひとつ前の記録は5/27。
A - そして蜃気楼といえばここ,SP-1600ポイント。ここからのひとつ前は5/12。
なお,アンチ蜃気楼条件の時ここからはどういう見え方をするのかの典型的なパターンとして,6/5の画像をあげておく。高島岬などなんにも見えない。(マチガイ:7/18)高島岬は見えます。見えないのは,トド岩などです。
2025.07.16版 鳥と虫,の巻 7/17 追補
コムクドリ
フキバッタ
チャドクガ電柱のコムクドリは7/4を最後に見かけない。寂しい。
と思っていたら,7/10,右岸でアオバトに出逢った帰り,聚富の田んぼ脇で10数羽のコムクドリの小さな集団に遭遇した。ほとんどは近くの防風林に逃げ込んだが,5羽ほどが電線にとどまる。もちろん電柱のコムクドリたちとは違うと思うが,あちらこちらに分かれて子育てし,巣立ちした幼鳥を鍛えながら小さな群れをなしているのだろう。
その後なんどか同じ場所を通りかかるが出会わない。今日(7/16)も試しに行ったが無駄足。蜃気楼に出会った。それは後で。
そして帰宅して自宅の庭にキリギリス,かと思ったけどどうやらフキバッタ。くっついたまま離れない。
【7/17 追補】 そして今朝,庭のモミジの幹に怪しげな虫影。調べてみると,今年幼虫が大発生したチャドクガの成虫。この角度からではよく分からないが,ちゃっかり2匹が寄り添っている。卵をやたら産みつけられたら,来年もまたとんでもないことになる。
2025.07.14版 1年ぶりに浜益まで,の巻
a
b
c
d
e
f一昨日(7/12)のこと。昨年7/30以来,ほぼ1年ぶりに浜益までの遠出。石狩市全域を軽いフットワークで網羅できなくなると,【花畔・網】も先が危うい。
(a) 雄冬岬の白銀の滝。昨年3月以来。往路,厚田の道の駅に立ち寄っただけなのだが2時間弱かかる。石狩市はやはり南北に長いね。
(b) 浜益・ふるさと公園から望む愛冠岬。当然"馬雪"はないが,雪が積もったら馬に変身するかもしれない裸地が斜面に確認できる。
(c) 浜益・岡島洞窟。すぐ脇を旧道が走っているが,落石工事中のコンクリート壁のため洞窟は見えない。上の画像は,やや高台になっているレストラン海幸の駐車場から見たもの。
(d) 荘内藩ハママシケ陣屋跡の大手門。ペンキが,古の遺跡感を損なっているのは否めない。中に入ってハママシケ陣屋の全貌。浜益ではあちらこちらにクマ出没の看板を見かけるが,ここには現われないのだろうか?
(e) 隣接する川下八幡神社境内に設置された望郷の石碑。鳥海山,湯殿山,羽黒山。この石碑はそこはかとなく好きだ。
大手門と石碑の移り変わりはコチラを見てほしい。
(f) 送毛山道(毘砂別送毛線)脇の千本ナラ。もとは3本の巨木が並んでいたが,2016年強風により真ん中の1本が倒れ,北側の1本も傾いて接近禁止。健在なのは南側のこの1本のみ。
2025.07.12版 今まさに見ごろ,の巻 3日目(7/7)以降
7/8
7/8
7/9
7/9
7/10
7/10
7/11
7/11
7/11
7/12
7/12
7/12げっぷが出るかもしれませんが,我慢してください。
当別の亜麻にはかなわない,かな? いいえ,負けてはいません。
でも今日は今年初めて浜益まで。昨年7/30以来,1年ぶりです。それはまた後で。
2025.07.10b版 右岸でアオバト,の巻
今日(7/10),下の7/10a版をアップした後,石狩川河口右岸へ。いつものように第二突堤つけ根近くの流木に腰かけて,キツネの仔でも現われないかなぁと,ボヤーっとしていたら,比較的大型の見慣れた鳥の群れ。アオバトでした。ここで出会うなんて思いもよらないこと。
第二突堤先端近くのテトラポットに止まってキョロキョロしています。慌てて撮りましたが,ピンボケの山。うまくいかないものです。
2025.07.10a版 はまなすの丘湿地帯の花,の巻
ノハナショウブ
タチギボウシ
アキカラマツ
カセンソウ7/7,砂嘴先端・はまなすの丘の湿地帯で出会った花たちです。一昨日,昨日は暑いさなか,家の内外でゴソゴソ片付け作業で大汗をかき更新が遅れてしまいました。
7/7の狙いは,6/24に咲き始めていたノハナショウブの絢爛豪華な大群落だったのですが,あにはからんや,終わっていました。やっと見つけたまとまって咲いていた花が上の画像です。
そのかわり,咲き始めたタチギボウシの群落に癒されました。
他には,アキカラマツとかカセンソウとか。これから8,9月にかけて湿地帯は賑わいを増すことと思います。
なおドクガのケムシ,めっきり減りました。木道の上では見つからず。もう蛹になったのかな・・・
2025.07.07版 亜麻開花3日目,の巻 石狩灯台保守作業
a
b
c
d(a,b) 今朝の亜麻,100ヶまで数えましたが情けなくもくじけました。200以上咲いていたに違いありません。
そして石狩の今日の最高気温は11時過ぎの32.9℃。そのころなにが楽しいのか,左岸砂嘴の先端をうろついていました。
別にとりわけ楽しいわけでもありませんが,北からの風が結構強くて気持ちいいのでした。
(c,d) 先端から戻ってくると,午後1時半の真っ昼間,灯台の灯火が灯っています。おや,海上保安庁のヘルメットも。保守作業だったようです。どさくさに紛れて入れてもらおうとしましたが,ダメでした。
2025.07.06版 亜麻開花2日目,の巻
2025.07.05b版 ショウドウツバメのヒナたち,の巻
a
b
c
d
e
f7/3大浜海岸のショウドウツバメのヒナたちです。飛び交う親鳥も少なくて,穴の入口に姿を見せたヒナたちもこれだけ。
(a~d)は同じ穴。ツバメも1日に1ヶずつ,合計で5~6ヶの卵を産むという話。順に孵化したとして,兄弟には生まれた順による序列が生ずるのかもしれません。この穴には少なくとも2羽のヒナがいるようですが,そのうちの1羽がずっと大きな顔をしていました。(e),(f)はそれぞれ別の穴です。
ところで穴の真上の崖の上に上がると,上から3~4ヶの穴が掘られていました。キツネの仕業かもしれません。そのうちの1ヶの脇には羽根が散らばっていました。可哀そうにやられたのでしょうね。
とにもかくにもバズーカみたいなカメラの砲列(といっても2,3人ですが)の中では,私のコンパクトデジカメではやや非力。尻尾を巻いて切り上げてきました。それよりなにより暑かった。
2025.07.05a版 今年も亜麻開花,の巻 昨年と同じ日です 5/26播種,5/31発芽
a
b
c
d今朝,ようやく5輪咲きました。昨年とまったく同日ですが,発芽からの日数は2日遅れです。
なんとなく気合イマイチだったのが響いたのかも。咲いたのは全部,お婆さんがタネをまいた部分。鼻高々です。草取りした功績は認めましょう。
来年も続けられるか,お爺さんは自信ありません。
とは関係なく,コムクドリの電柱はスズメたちが我が物顔です。
2025.07.03版 コムクドリの姿が消えた,の巻 総集編 7/4 追補
このページについてお気づきのことがありましたらお知らせください
トピックス 目次